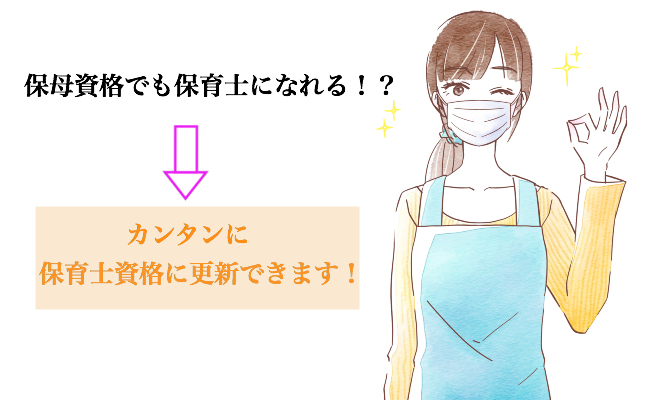
保育士は、かつて「保母」と呼ばれる時代がありました。
現在「保母資格」では保育現場で働くことはできません。
しかし、簡単な手続きをすることで、保育士資格に切り替えられることをご存知でしょうか?
今回は、保母資格から保育士資格への切り替え手順や、復職する際のポイントなどをご紹介いたします。
眠らせている保母資格を、再び保育の現場で活躍してみませんか?
保育施設や養護施設など、児童福祉施設で働く人を「保育士」といいます。
保育士は国家資格であり、「保育士資格」を取得することで保育士を名乗ることが可能です。
一方「保母」とは、「保育士」以前に呼ばれていた名称です。
保母であったころと保育士では、仕事内容は変わりませんが、現在は保母資格で働くことはできません。

現在の保育園のような施設は昔から存在し、女子であれば誰でも保育施設で働けました。
しかし、1948年に児童福祉法が制定され、高等学校卒業が条件となる保母資格取得証明書が必要であると定められます。
保育の専門職化の始まりです。この証明書をもつ女性は「保母」と呼ばれました。
1977年の児童福祉法の改正により、保育施設で働く男性も「保母に準ずるもの」として「保父」という呼称が認められました。
また、女性のみの資格であった保母資格取得証明書を男性も取得が可能になったのです。
そして1999年、「保母」「保父」ともに性別による名称の違いのない「保育士」へと呼称が変更になりました。
その後、2003年には児童福祉法の改正で保育士資格は国家資格となり、正式に専門職として定められたのです。
保育士資格を取得するためには、各都道府県知事に資格の登録手続きを申請し、保育士証の交付が必要です。
また、国家資格へと変更になるのと同時に、保育の知識や技能の向上など、保育士の資質も求められるようになりました。
2003年の児童福祉法の改正は、「保育士」の国家資格化にともない、保育士資格の条件も大きく変更となりました。
つまり、保育をするという業務内容は変わらないもの、「保育士資格」と「保母資格」はまったく異なるものとして定義されたのです。
そのため、保育士資格取得証明書だけでは、保育の業務に就けなくなりました。
保母資格には、継続のための手続きなどはなく、また有効期限もないので一度取得した資格はずっと有効です。
しかし、再び保育施設などで働く場合には、保育士資格への切り替えが必要。
保育士登録への期限はありませんが、もし今後保育士として業務に就く可能性があれば、事前に資格の切り替えをしておきましょう。

保母資格を保育士資格へと切り替えなければならないことは知っていても、「どのように保育士資格に切り替えればよいのか分からない…」という方も多いのではないでしょうか。
手続きは必要ですが、特に難しいものではありません。
「保育士登録手引き」の取り寄せ
登録手数料の振込み
必要な書類を用意
登録事務処理センターに書類提出
切り替えの手続きは以上です。順を追ってご説明していきます。
保育士資格への切り替えは、都道府県から委託を受け日本保育協会が運営している、
登録事務処理センターから行えます。
登録事務処理センターでは、このほかにも保育士証の再交付や、保育士証の書き換えが可能です。
保母資格からの切り替えで必要な「保育士登録手引き」を受け取るための方法は、封筒のサイズまで細かく決められています。
手順1:送信用封筒の宛先に「〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階 登録事務処理センター」と記入し、必要金額分の切手を貼る。
手順2:送信用封筒ならびに返信用封筒に、赤字で「保育士登録の手引き○部」と請求内容を明記する。
手順3:返信用封筒に住所、郵便番号、氏名を記入し、請求部数に応じた郵便料金の切手を貼る。
手順4:切手を貼った返信用封筒を、送信用封筒に入れる。(返信用封筒は折りたたんで入れてもかまわない)
手順5:送信用封筒に封をし、郵便ポストまたは郵便窓口から郵送する。
保育士登録手引きには、専用の払込用紙が同封されています。なお手数料は、登録1人につき4,200円です。
手順1:氏名を記入する3ヵ所すべてに申請者本人の住所、氏名を記入する。
手順2:郵便局に行き、窓口で払込手続きをする。
※ATMでの払込手続きは不可。必ず窓口で手続きをする。
支払い後に受け取る「振替払込請求書兼受領証」と、「振替払込受付証明書」両方の郵便局の日付入り受付印が押印されていることを目視しましょう。
「振替払込請求書兼受領証」は、郵便事故などが起こった際に、支払いを証明する書類なので、保育士証が届くまでは大切に保管してください。
もう1つの「振替払込受付証明書」は、保育士登録申請に使用します。
登録手数料を振り込んだら、必要な書類を用意しましょう。
「保育士登録の手引き」に同封されている申請書類です。
手数料払込用紙についていたものです。
手数料の支払い後、保育士登録申請書の裏面にのりで貼り付けてください。
保母資格からの切り替えの場合、必要なのは「保育士(保母)資格証明書」です。
平成15年11月29日までに交付されたものが対象となっています。
※結婚などで「保育士(保母)資格証明書」と現在の氏名が変わっている場合
現在の戸籍抄本が必要です。
有効なのは、発行から6カ月以内の戸籍抄本のみ。
コピーではなく、必ず原本を提出しましょう。
必要な書類が用意できたら、登録事務処理センターに提出します。
【提出先】
申請書類は、都道府県の委託を受けた登録事務処理センターで受け付けています。
必ず以下の宛先に郵送しましょう。
登録先の都道府県では登録事務を受け付けていませんので、注意してくださいね。
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階
登録事務処理センター
【提出方法】
申請書類郵送の際は、必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便を利用しましょう。
郵便局窓口で発行される「書留郵便物受領書」は、保育士証が届くまで大切に保管してください。
郵便事故が起こった場合には、提示する可能性があります。
【書類不備の場合】
書き漏れや間違いなど、書類に不備がある場合は、登録事務処理センターから連絡が来ます。
書類不備の場合は、保育士証の交付が遅れる可能性も。
申請書類を郵送する際は、記入漏れや添付書類の不足がないか、必ず事前に目を通しましょう。
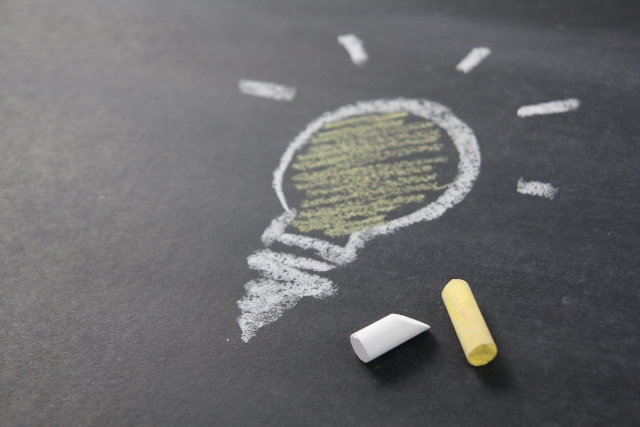
申請書類は、都道府県により審査に通れば、各都道府県の備える保育士登録簿へ情報が登録されます。
その後に保育士証が交付され、登録事務処理センターから簡易書留郵便で郵送される仕組みです。
提出から保育士証が交付されるまでは、2カ月程度かかります。
もし、申請書類を郵送してから3カ月以上経過した場合は、登録事務処理センターに問い合わせしましょう。
書類に不備があるのかもしれません。
申請書類を郵送した際、郵便局窓口で発行された「書留郵便物受領書」
手数料払い込みの際に郵便局窓口が受付印を押印した「振替払込請求書兼受領証」
以上の書類を用意しておくと、問い合わせがスムーズです。
無事に保育士証が手元に届けば、保育士として復職できます!
保母資格からの切り替えは少し時間が掛かりますが、試験などはなく手続きのみでできます。

保育士証への切り替えが完了し、いよいよ保育士復帰へ。
久しぶりの就職活動は、どのように仕事先を選べばよいか悩みますよね。
ブランクのある方が、スムーズに保育士復帰するための取り組みを一部ご紹介いたします。
長く現場を離れていると、復職する時に不安を感じやすいものです。
昔のやり方が通用しないかも
就職活動自体に不安がある
このような悩みを抱えている場合には、各自治体で行っている保育士の復職支援を受けてみるのも1つの選択肢です。
たとえば、東京都では保育に復職したい方を対象としたセミナーや人材あっせんをしています。就職相談などもしているので、1人での職場探しに不安を感じている方には心強いですね。
就職前には、どのような働き方をするのか決めておくことが大切です。
通勤時間も含めて自分に合った勤務時間や雇用形態を選びましょう。
就職活動に入る前に事前に家族で話し合っておくと、スムーズに進めやすくなります。
また、保育士の業務は、今も昔も体力勝負。
無理のない短時間勤務から保育士復帰し、徐々に時間を増やしていくのも1つの手です。
職場選びの際は、できるだけ見学をするとよいでしょう。
保育施設の様子や働きやすさは、求人情報だけでは読み取ることが難しいからです。
【見学から得られる情報】
どのような保育をしているか
子どもの雰囲気
職員同士のやりとり・人数配置
水回りなど衛生面への意識 など
見学した時に得られる情報は、意外に多いものです。
働いてから「なにか違う」という違和感を減らすためにも、事前の見学をおすすめします。
保育士への復職については、「保育士として復職したいけどブランクがあっても大丈夫?事前に押さえるべきポイントを解説」でさらに詳しく解説しています。
合わせてご覧ください。

今も昔も、社会のなかで重要な役割を担っている保育士。
しかし近年、保育士不足は大きな問題となっています。
現在、保母資格のままでは保育施設で働けませんが、簡単な手続きをすることで保育士として復帰できます。
保母資格のまま眠らせているのはもったいないです。
各都道府県で保育士復帰への支援が取り組まれているように、保育士への復帰は国からも歓迎されています。
保育士復帰セミナーなども利用しながら、過去の経験をいかせる職場で保育士復帰を目指しましょう。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.