
保育士は子どもと接する仕事のため、言葉遣いにも気を払わなければなりません。しかし、どんな言葉が適切で、どんな言葉を避けるべきなのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、保育士にとっての適切な言葉遣いについて、また、避けるべき言葉遣いについて「子ども」と「保護者」に分けて具体的に解説いたします。相手別に見ていくことで、保育士の言葉遣いについてより深く知ってもらえるはずです。これから保育士を目指す方も、今実際に保育士をされている方もぜひ参考にしてください。

言葉遣いとは「ものの言い方」「言葉の使い方」のことです。私たちが普段何気なく使っている言葉も、保育の現場ではふさわしくない場合があります。また、子どもの発達にとっても保育士の言葉が大きな影響を与えることを忘れてはいけません。
さらに、保育士は専門性のある仕事です。そのことを念頭に保育をする必要があります。その場にふさわしい言葉遣いをすることによって、保育の質も高まります。そのため、自分の口から発する言葉遣いに責任を持つことが大切です。ただし、これは保育の仕事だけではありません。その場所、人にとってどのような言葉遣いがふさわしいのかを考え、いつでも適切な言葉を使えるようにしましょう。

ではここで、実際にどのような言葉遣いを避けるべきかを解説していきます。これらは普段の保育でぜひ気をつけてもらいたい言葉です。避けるべき言葉遣いは不適切な保育にもつながる恐れがありますので、よく確認して普段の保育から気をつけるようにしましょう。
まず、子どもに向けての避けるべき言葉遣いを解説いたします。悪気がなくてもつい使ってしまいそうになることもあるかもしれません。ぜひこの機会に保育士としての言葉遣いに目を向けてみてください。
もし自分のやっていることが否定されたらどんな気持ちになるでしょうか。子どもも大人と同じ気持ちです。「〇〇くんはできないね」「できないからやらなくていいよ」などの否定的な言葉は子どもの自己肯定感を低くし、子どもとの信頼関係も失ってしまいます。
多様化する社会の中で外見にまつわる言葉は注意が必要です。大人からみるとかわいらしいと感じる部分であっても、本人にとっては嫌なこともあります。現在では「ルッキズム」といって、見た目で人を判断したり、差別をしたりするという行為を見直す動きが出てきています。何気ない言葉で子どものコンプレックスを生み出さないように十分注意しましょう。
「お友だちはできているけれど〇〇君はできていないのね」など、誰かと比較する言葉は適切ではありません。誰かと比較されて育った子どもは、成長にともない他人との比較によってしか自分を認めることができなくなってしまいます。家庭で兄弟や姉妹と比較されることが多い園児の場合は特に注意しましょう。
「〇〇ちゃんってお猿さんみたい」「歩き方がクマみたいだよ」などと比喩的な言葉を子どもたちに使うことはやめましょう。もちろん表現遊びの中で、みんなで楽しむなどのねらいをもって行う場合は別ですが、普段の生活の中でからかう意味を含んで使うことは不適切な保育となり得ます。
「仲良くしないとおやつの時間にならないよ」「静かにしないと鬼が来るよ」などの強迫する言葉は保育にふさわしくありません。おやつが食べたいから仲良くしたり、鬼が怖いから静かにしたりするという間違ったモラルを学んでしまうことになります。保育にとって大切なことの1つは、子どもたちの未来を考えることです。将来どんな人になっていて欲しいかを考えて言葉を選んでいきましよう。
子どもにとって保育士は大人のモデルです。保育士から大人を学んでいるため子どもは保育士のまねをします。また、多くの言葉を吸収する時期にどんな言葉遣いが大切かはすでに分かっているはずです。乱暴な言葉からは乱暴な言葉しか生まれません。「邪魔だよ」「どけ」などの言葉は絶対に言わないようにしましょう。また、怒りの感情から保育にふさわしい言葉やよい保育は生まれません。
では次に、保護者の方に向けての避けるべき言葉遣いをお伝えいたします。基本的に保護者の方も子どもと同じで、もし自分だったらどんな言葉をかけてもらいたいかを考えてみるとよいでしょう。
「今日〇〇はこうだったよ」や、「明日はこれ用意してね」など、保護者の方との距離を縮めたい理由で、友だちのような言葉遣いをすることはふさわしくありません。保育士と友だちのような関係を快く思わない保護者の方もいます。あくまでも「先生」と「保護者」という関係を守り、丁寧な言葉遣いをするようにしましょう。
保育者が上から目線でものを言うことも避けなければなりません。「今日は〇〇してあげました」などの言葉遣いは保護者の方にとって気持ちのよいものではありません。保護者の方との信頼関係が壊れてしまうと、その後の保育もやりづらくなってしまうため注意が必要です。
否定的な言葉を言われて気持ちのよい人はいません。逆接を表す「それでも」「そうかもしれませんが」などの言葉はできるだけ使わないように気をつけましょう。また、失敗をしてしまったときには、言い訳をしたり、なんだかんだと理由を並べたりするのではなく、事実をしっかりと伝えるようにしましょう。保護者の方とよい関係を築けるように言葉遣いに気をつけることはとても大切です。
保育士に限らず普段の生活の中で「やばい」を多用する風潮が見受けられます。おいしいものを食べても、きれいな景色を見ても「やばい」を使って表現する場合が多いようです。
この「やばい」には多くの意味が含まれていることは理解できますが、子どもにとってはどうでしょうか。
その物事にあった適切な形容詞を選んで使うことをぜひ行ってみてください。たくさんの語句を知ることは、子どもの成長にとって不可欠です。そのためにも保育士は自らの言葉遣いに気をつけ、子どもたちによい影響を与えられるような言葉遣いをするようにしましょう。

ここまで、保育にネガティブな要素である避けるべき言葉遣いについて具体的にご紹介してきました。では、保育士が使う正しい言葉遣いとはどのようなものなのでしょうか。ここからは正しい言葉遣いについて具体的にご紹介していきます。すぐに実践できるような言葉ばかりです。ぜひ参考にしてください。
ここでは子どもに向けての正しい言葉遣いをご紹介いたします。正しい言葉を使うことは、子どもにとって保育士がよい人的環境になることを意味しています。では、どのような言葉遣いがふさわしいのかご紹介していきましょう。
「すご〜い」「じょうずだね〜」などの褒め言葉を使っている保育士も多いのではないでしょうか。もちろんこのような言葉遣いが悪いわけではありません。ただ、もう少し具体的に褒めることを意識してみましょう。「折り紙が前より上手に折れるようになってすごいね」など、語尾を伸ばさずにきれいな日本語で褒めることが大切です。
子どもの気持ちに寄り添って共感することはとても大切です。特になかなか言葉をうまく使えない年齢の子どもには、保育士の共感の言葉が何よりも安心感を与えます。ただし、「お友だちにおもちゃを取られちゃって、まだ遊びたかったのに悲しかったよね。返してって言っても返してもらえなかったんだね」などのように子どもの心を解説する必要はありません。自分だったらどんなふうに共感してもらいたいかを考えると、子どもに寄り添える言葉遣いが見つかるはずです。
言葉の魔法によって、子どもはいつも以上の力を発揮できるときがあります。「今度は絶対できるよ」「頑張っていること知っているよ」などの言葉によって子どもたちはやり遂げる力を身につけることができます。励ましたり、期待したり、保育士はどのような言葉遣いが適切かを考え、声かけする必要があります。
保護者の方にも子どもと同じように正しい言葉遣いで接することはとても大切です。また、保護者の方だけに対して正しい言葉遣いでもよくありません。子どもに向けても、保護者の方に向けても正しい言葉遣いをすることは必要ですが、ここでは主に保護者の方に対するふさわしく正しい言葉をご紹介いたします。
「〜です」「〜ます」など、語尾を丁寧にすることで保護者の方に対する言葉遣いがよくなります。その他、尊敬語や謙譲語なども自然に使えるようになるとますます印象がよくなることでしょう。言葉遣いはとても難しいですが、保育士の質も見定められることになりますので、ぜひ気をつけるようにしましょう。
子どもをあだなで呼ぶことで親しみを伝えたいと考える保育士もいるのではないでしょうか。ただし、子どもの呼び方は保育士全員で同じにすることが大切です。「○○ちゃん」や「〇〇くん」などと全員が同じ呼び方をすることで保護者の方は安心感を持つことができます。
呼び方が違うことで、あの先生は子どもをひいきしているなどという噂にもつながってしまうかもしれません。保護者の方に不安や疑問を与えないようにしましょう。
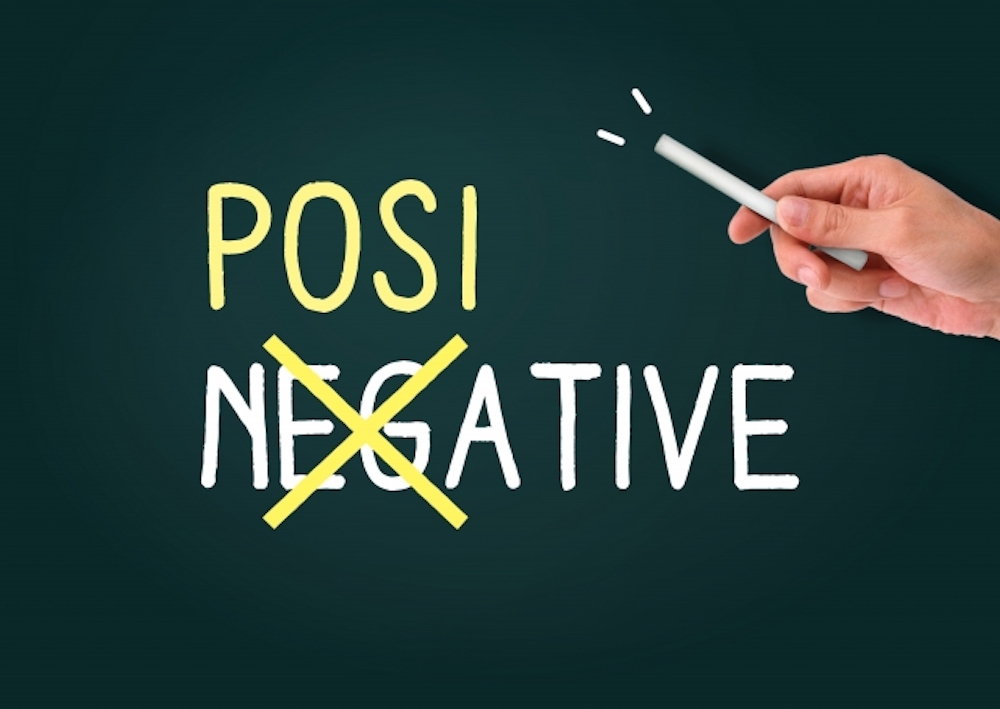
たくさんの言葉が保育の中で使われていますが、積極的に使ってもらいたい言葉もあります。また、言い換えることで、保護者の方との関係をよりよくできる言葉もあります。ここでは、ぜひ使ってもらいたいという言葉を具体的にご紹介いたします。
保護者の方との会話の中で、「でも」などの否定的な言葉を使いたくなるときがあるかもしれません。そのようなときはまず最後まで話を聞いて、保護者の方への共感を表してから、「実は」と切り出すとよいでしょう。保護者の方も話を最後まで聞いてもらうことで保育士に信頼を持てるようになるはずです。
保護者の方から子どもの発達についてアドバイスを求められたとき、「こんなことができる子どもが多いです」と言ってしまいがちです。保護者の方はそう言われたことで、子育てに自信をなくしてしまうこともあります。そのため、子ども同士を比較する言葉は使わないようにしましょう。「ほかのお子さんはどうですか」などとたずねられたら、「こんなケースが多いです」と言い換えてソフトに伝えるようにしましょう。
もし保護者の方から間違いを指摘されたら、さまざまな理由をつけて曖昧にすることはやめましょう。また、「間違えていません」などと強く言うことも避けた方がよいでしょう。間違えていない確信があるときは、「すぐ確認いたします」と伝えましょう。もし、間違っているかもしれないと不安なときは、「私が間違っているかもしれません」などと素直に気持ちを伝えることが大切です。
言葉は表現のひとつです。自分の思いや考えを伝えるときには言葉が必要です。その言葉をより丁寧に考えて話すことは相手を敬うことにつながります。逆に、言葉は相手に対しての武器になってしまうことも忘れないようにしましょう。不適切な保育は態度だけでなく、言葉も含まれます。
子どもを一人の人として関わることができるのが保育者の専門性であることを忘れないようにしましょう。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.