
保育士として働いている人の中には、パワハラで悩んでいる人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、パワハラの具体例・対処法についてご紹介いたします。今現在パワハラで悩んでいる人にも、もしくはパワハラの現状を知りたい人にも役に立つ内容です。さらに、パワハラと指導の線引きについてもお伝えしていきます。ぜひ参考にしてください。

ここではパワハラの定義についてお伝えいたします。パワハラとはパワーハラスメントの略で、職場の中での立場を利用した適正な範囲を超えた叱責や嫌がらせのことです。
厚生労働省では、パワハラの概念として3つの要素を挙げています。それらの要素を満たした6つの行為がパワハラに当てはまります。これらをよく理解しておくことはパワハラの抑止にもつながります。ぜひどのような要素と行為がパワハラに当たるのかを理解しておくようにしましょう。
厚生労働省はパワハラの定義を示しています。その中には職場におけるパワハラについて3つの要素が書かれています。そして、その3つの要素すべてを満たすものを職場のパワハラの定義としています。では、その3つの要素について見ていきましょう。
職場内での優位的な立場を利用して、強い立場の人が抵抗や拒絶することができない弱い立場の人に対して行われるもののことです。年齢だけのことではないため、同僚や後輩からパワハラを受けることも含まれます。
業務上必要のない言動や、仕事の指導の範囲を超えて行われる言動などをパワハラの要素のひとつとしています。適正であるかどうか、理不尽であるかどうかは自分自身が一番よく分かることでしょう。
暴力や暴言、執拗な叱り方など精神的や身体的な苦痛を与えることも要素のひとつです。嫌なことを言って職場で働きにくくさせる行為もパワハラです。
そして、厚生労働省ではパワハラの種類を主に6つ挙げています。より具体的に示されているこれらの行為はパワハラに当たる可能性があります。
殴ったり、蹴ったり、小突いたりする行為です。身体に暴力を振るうことがこれに当たります。体罰も同様です。
これは執拗に叱責や暴言、脅迫を行うことを指します。また、子どもの前で叱ることもこれに当たります。そのほか、人格を否定することや、家族に対しての悪口、目の前でため息をつくことも精神的攻撃です。
人間関係の切り離しとは仲間外れのことです。意図的に打ち合わせから外したり、わざと仕事を割り振らなかったりすることもこれに相当します。
指導もなく新人の保育士に担任をさせたり、自分の仕事以上のものを割り当てたりすることを言います。強制的に休日出勤をさせることも過大な要求のひとつです。
経験も実力もある保育士に、保育をさせずに掃除をさせるなど本来の保育ではなく、保育以外の仕事をさせることです。
プライベートなことに関して執拗に問いただしたり詮索したりすることです。私物を勝手に触ったりすることも個の侵害に当たります。
【参考】厚生労働省リーフレット「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
ここまで厚生労働省が定義するパワハラついて解説してきましたが、これらが実際保育園ではどのような形で現れているのでしょうか。
保育園でパワハラをするのは園長や主任などが多いと言われています。優位な立場を利用して、休みを取らせなかったり、子どもの前で罵倒したりすることが保育園特有のパワハラです。また、指導と称して叱ったりすることもその叱り方によってはパワハラに当たります。
では次に、パワハラと指導の違いを知るために具体的な例を挙げていきます。
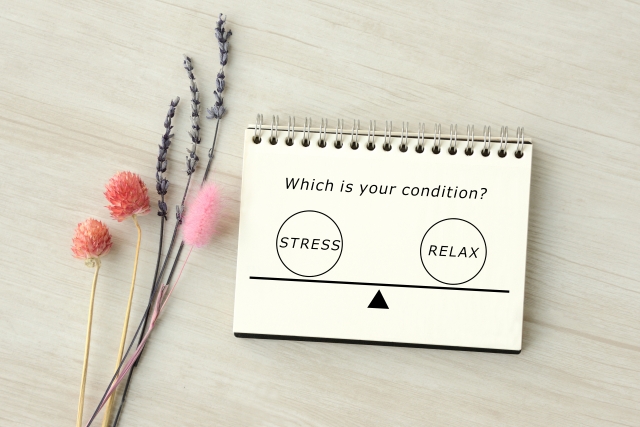
パワハラを行いながら、「これは指導だから」と言われる場合も多いのが現状です。しかも、先ほどご説明した3つの要素すべてが満たされないとパワハラと判断されません。
ここからはパワハラの具体例をご紹介し、パワハラと指導の違いをお伝えいたします。
ここからの具体例は3つの要素がすべて満たされているものです。指導との違いを知って、自分が受けているものがパワハラかどうか判断するのに使ってみてください。
そのときの感情で子どもの前で怒鳴ったり、ヒステリックに叱ったりすることはパワハラに当たります。指導であれば、子どものいない場所で落ち着いた口調で注意をするはずです。子どもの前で担任が異常に叱られると、子どもたちにとっても悪影響になります。
無視は精神的にダメージを与えるパワハラのひとつです。心の負担は大きく、いじめのひとつと言えます。指導において無視をすることは絶対ありえません。子どもの心身の成長を見守る保育の現場で保育士の精神を病むような行為は絶対に行われてはいけません。
人は誰でもミスをしますが、そのミスに対しての指導ではなく、人格を否定するような注意の仕方もパワハラに当たります。たとえば、「あなたの性格が悪いからミスをする」や、「あなたの親の育て方が間違っている」などです。ミスに対してだけ注意することが指導です。人格を否定されるようなことがあればそれはパワハラと言えるでしょう。
ほかの保育士の責任で起こったトラブルに対して、一方的に責任を押し付けられることはパワハラと言えます。怪我をしてしまった子どものことや、保護者からのクレームなどに対して、問題解決もせずに責任を転嫁するような職場では働く意欲もなくしてしまうでしょう。本来なら、園長や主任も加わり、誠意ある対応を取りつつ事実確認などもしっかりと行うはずです。
時間外に仕事をすることを強制したり、休みの権利を害したりすることもパワハラに当たります。異常な労働環境では心も身体も疲れてしまい、よりよい保育をすることが難しい状態に陥ってしまいます。また、理由もなく減給することもパワハラです。園の総責任者として園長は働きやすい環境を提供する責務があります。このように異常な労働環境を作り出すことはパワハラと言えます。
パワハラと指導の線引きは難しいと感じる場合もあるでしょう。しかし、指導の場合には必ずそこに保育士への心遣いがあります。また、築き上げてきた信頼関係を壊さないように言葉も選んでいるはずです。1人の人間として人権が守られるような関わりの仕方であればそれは指導です。保育士の成長を願って注意することもありますが、そこには最大限の気配りがあることが大切です。

ここまで、パワハラについてその定義や具体的な事例についてお伝えしてきました。もし、心当たりがあるようでしたら、今すぐに解決することが必要です。
では、実際に解決するためにはどうしたらよいのでしょうか。ここではパワハラの解決のために有効な方法をご紹介いたします。
一人で悩んでいる時間が長いと、いつの間にか心身を病んでしまう場合があります。そうならないためにも信頼できる人に相談することをおすすめします。自分の園とは全く関係のない人でもよいですし、内部事情を知っている同僚や先輩などに相談するのもよいでしょう。その場合、秘密を絶対に漏らさないことを確認しておく必要があります。自分の状態を理解してくれている人がいるだけで、心強いのではないでしょうか。
公共機関に相談することもパワハラを解決するための方法のひとつです。労働基準監督署の労働相談コーナーでは、パワハラについての相談をすることができます。労働基準法に基づいてアドバイスや指導をしてくれます。状況によっては行政機関へつないでくれることもあります。労働相談コーナーは厚生労働省が各自治体に設置しています。
【参考】厚生労働省 総合労働相談コーナー
公共機関に相談する場合、証拠があることで、優位に話を進めることができます。そのためにも証拠を集めておくことはとても重要です。特に、録音や録画はパワハラの客観的な証拠になりえます。そのほか、暴力によって通院した場合は診断書も用意しておきましょう。また、ノートにパワハラを受けた日時や状況を書き留めておくことも大切です。
辛い職場環境での勤務に耐えられなくなったときは、ほかの園への転職も考えてみましょう。その際には「ジョブトル保育」にぜひ相談してみてください。ジョブトル保育では事前に園見学ができます。園見学によってパワハラを避けられる可能性を高めることができます。さらに専任のコンサルタントがサポートしてくれるため、自分の希望に近い職場を紹介してもらえます。その上、コンサルタントを経由して直接話しづらいことでも希望園に連絡してもらえるため、安心して質問することもできます。自分の理想に近い園に出会えるかもしれませんよ。
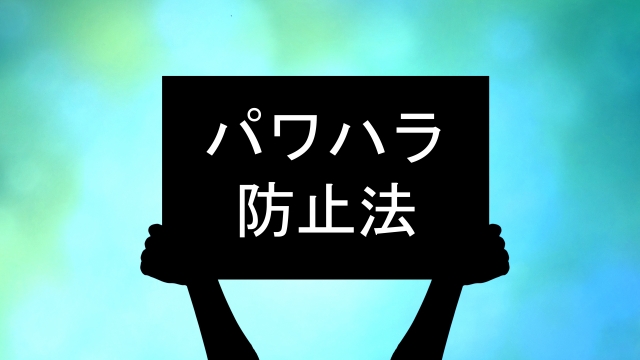
保育者がパワハラを受ないように国や保育園でもパワハラに対する対策を行っています。ここでは、どのような対策が義務づけられているかをご紹介いたします。
パワハラが大きな社会問題となったため、2020年の6月からパワハラ防止法が施行されました。このことでパワハラの防止を企業に義務づけることになりました。2022年4月からは中小企業にも防止措置が義務づけられています。
では、具体的にどのような対策が義務づけられているのでしょうか。
まず1つ目は、園としてパワハラ防止に対してどのように考えているかを明確にすることです。パワハラを行ってはならないこと、そのためのガイドラインを共有し、周知させることを義務づけています。
2つ目には、相談窓口の設置と利用方法の周知です。園内の職員の中から担当者を任命したり、外部機関へ委託をしたり、相談ができる環境をつくらなければなりません。相談窓口の担当者は研修を受け、よりよい解決策が見つけられるようにしなくてはなりません。
3つ目は、もしパワハラが確認された場合、被害者に配慮し、迅速にかつ正確に対応できる体制を整えることができる流れを決めておくことです。
そして、以上の3つのことについてプラバシー保護のマニュアルを作り、研修等を行うことも必要だと定められています。
残念ながら、現状では違反した場合の罰則はありません。しかし、パワハラの事実を労働基準監督署に通報し、指導や勧告を受けても改善がされない場合は、園名の公表が行われます。そのことで、社会的信用を失うことも考えられます。パワハラは個人的にも社会的にも大きな問題で、許されないことを保育園側は忘れてはいけません。
保育士は子どもと関われる素晴らしい仕事です。ですが、大人の社会でパワハラが行われていると、絶対的に保育の質向上は期待できないため、仕事を楽しむこともできないでしょう。また、大人は子どものモデルです。そのような自覚を持つ保育士が多い園では、パワハラは生まれにくいと言えます。パワハラを生ませない、許さない、そのような環境に恵まれることによって、保育士として生き生きと活躍できるはずです。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.