
保育士にとって、名札は子どもたちに名前を覚えてもらうためのマストアイテムです。保育園によっては就業や保育実習時に手作りのオリジナル名札を求められる場合があり、作り方やデザインに悩みを抱えている方も多いことでしょう。
そこで当記事では、手作業で簡単に仕上げられる、保育士の名札の作り方を詳しくご紹介いたします。素材選びやかわいいデザインにするコツ、名札作りの注意点なども詳しく解説いたしますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

まずは、保育士が名札を手作りする際に押さえておくべき注意点から確認していきましょう。
名札の仕様について、保育園ごとに規定が設けられている場合があります。規定に沿わない名札だと、せっかくアイデア豊かに作っても使えない恐れがあるため注意が必要です。
名札作りを開始する前に、下記の注意点をしっかりと押さえておきましょう。
保育園によっては名前の表記方法が決められているケースがあります。名前をひらがなで書くのか漢字で書くのか、フルネームなのか名字または下の名前だけなのかなど、事前にしっかり確認しておきましょう。
名前についてとくに規定が設けられていない場合には、数パターン用意しておくと安心です。先輩保育士が付けている名札を参考にするのもよいでしょう。
簡単に取り外しのできる、名札の留め具として定番の安全ピンですが、針がふいに外れてしまう危険性があるため、保育園によっては禁止している場合があります。そのため、名札に安全ピンを使用できるかどうかを必ず事前に確認しておきましょう。
安全ピンが使える場合でも、針が外れにくいロック機能が付いたものや安全カバーを搭載したものなど、安全性の高い製品を使っておくとより安心です。
なお、安全ピンが使用できない保育園の名札は、アイロン接着マジックテープやスナップボタンを留め具に用いたり、エプロンに直接縫い付けたりするのが一般的です。
【参考】クロバー株式会社「ロックピン(大) 品番 : 26-307」
クロバー株式会社「安全ロックピン カバー付 品番 : 26-309」
アニメや絵本に登場するキャラクターは、子どもたちの興味を引きやすい人気のデザインです。しかし、保育園の方針により、キャラクターモチーフの名札が禁止されている場合もあるため注意が必要です。
名札のデザインを決める前に、キャラクター使用の可否を必ず確認しておくようにしましょう。
名札の大きさも、作る前に保育園へ確認しておくと安心です。
とくに規定がない場合には、大人のこぶし1個分程度の大きさにするのがおすすめ。子どもたちはもちろん、保護者の方も見やすいよう、名前の部分はとくに大きくスペースをとり、はっきりとした文字で表示するようにしましょう。
名札には、子どもが触れたり万が一口にしたりする可能性を考慮して、布やフェルトなどのできるだけ安全な素材を選びましょう。
布やフェルト製の名札なら汚れた際にも洗えるため、長く衛生的に使っていけるのもメリットです。
なお、ボタン・ビーズ・ラインストーンなどのデコレーションパーツは使用しない方が無難でしょう。硬い素材のため、遊んでいる最中や抱っこ中などに子どもに当たると、ケガをさせてしまう危険性も。パーツがふいに外れてしまった場合には、誤飲につながる恐れもあります。
なお、名札に使用する素材は、布などの安全なものであっても、アイロンや接着剤でしっかりと貼りつけたり、針と糸で縫い付けたりして、剥がれないよう丈夫に仕上げておきましょう。
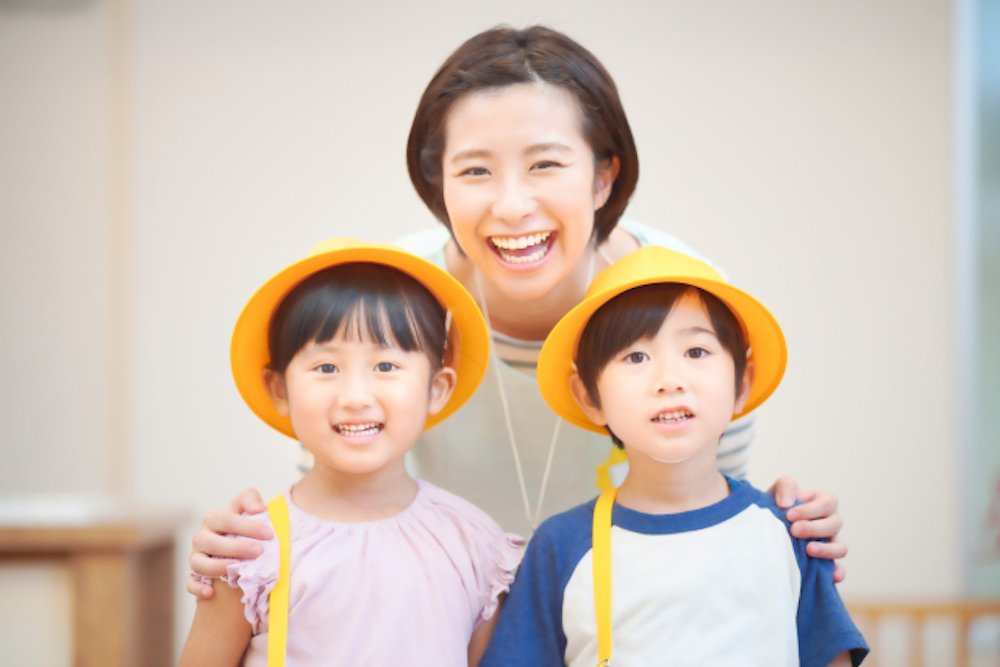
せっかくオリジナルの名札を作るなら、子どもたちの心をグッとつかむかわいいデザインに仕上げたいですよね。
そこでここからは、名札のかわいいデザインを決めるコツをご紹介いたします。
アニメや映画、絵本などに登場するキャラクターモチーフの名札なら、子どもたちの目に留まりやすく、コミュニケーションをとるきっかけとしても活用できます。
ただし、キャラクターデザインを取り入れる場合には、性別や年齢を問わず子どもたちみんなが知っているような、幅広く人気のあるものを選ぶようにしましょう。
たとえば、アンパンマンやドラえもん、となりのトトロなどが定番です。ディズニーやサンリオキャラクター、絵本のはらぺこあおむしなども人気を集めています。
なお、前述の通り、保育園のなかにはキャラクターデザインの名札を禁止している施設もあるため注意が必要です。キャラクターを用いる場合には、必ず事前に使用の可否を確認しておきましょう。
動物モチーフの名札は、かわいらしい雰囲気に仕上げられるのが魅力です。
乳幼児クラスにはひよこ・りす・小鳥などの小動物、幼児クラスにはぞう・パンダ・くまなど大きな動物など、子どもの年齢のイメージに合わせていくつかの動物名札を作っておくのもおすすめです。動物なら流行の移り変わりなどがないため、一度作れば長く使っていけます。
また、動物は子どもたちに人気の歌や絵本などに多く登場するため、保育に活用できるのもポイントです。たとえば、たぬきがモチーフの名札を作れば「げんこつやまのたぬきさん」や「しょうじょうじのたぬきばやし」などの手遊び歌に使えますし、たぬきが出てくる絵本を読む際には登場キャラクターの一匹としても活用できます。

名札作りの注意点やデザイン選びのコツを押さえたところで、ここからは早速、保育士の名札の作り方をご紹介いたします。
アイロンや接着剤のみで仕上げる【初級編】、針と糸で手縫いする【中級編】、裁縫が得意な方向けの【上級編】とレベル別に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
まずは、アイロンや布用接着剤を使って仕上げる、裁縫初心者の方や苦手な方などにおすすめの【初級編】の作り方から見ていきましょう。
初級編の名札を作る際に準備しておくと便利な材料は次の通りです。
型紙は、自分でデザインするほか、無料イラスト素材サイトなどを検索して好みのものを参考にするのもおすすめです。
初級編の名札は短時間で仕上げられるのもポイント。名札作成になかなか時間が取れない方にもぴったりです。
【POINT】名札の土台となるパーツは、重ねて丈夫に仕上げるため、同じものを2枚用意しましょう。
【POINT】パーツごとに細かくアイロンをかけて接着していくと、失敗が少なく、よりキレイに仕上がります。

つづいて、針と糸を使って作る【中級編】の作り方を見ていきましょう。
中級編の名札を作る際に準備しておくと便利な材料は次の通りです。
中級編の名札は、針と糸で各パーツの周囲をしっかりと縁取りするため、丈夫な名札に仕上げられるのが特徴です。
【POINT】名札の土台となるパーツは、重ねて丈夫に仕上げるため、同じものを2枚用意しましょう。
【POINT】フェルトを刺繍糸で縁取りする際には、フェルトの縁を糸で巻くようにして縫いあげる「ブランケットステッチ」がおすすめです。
最後に、針や糸、フェルトなどの基本素材に、綿をプラスして仕上げる【上級編】の作り方を見ていきましょう。
上級編の名札を作る際に準備しておくと便利な材料は次の通りです。
フェルトの間に綿を詰めればふっくらと立体的でよりキュートな雰囲気に仕上がります。
【POINT】名札の土台となるパーツは、間に綿を挟むため、同じものを2枚用意しましょう。
【POINT】フェルトの縁を糸で巻くようにして縫いあげる「ブランケットステッチ」がおすすめです。
保育士が名札を手作りする際には、自分自身も付けるのが楽しくなるようなかわいいデザインを取り入れるのがおすすめです。
布用ボンドを使ったり、刺繍糸や綿を使ったりと作り方はさまざま。ぜひ、ムリなく楽しみながら作れる方法で、子どもたちの印象にも残るすてきな名札を作ってみてください。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.