
難易度が高いと言われている保育士試験。これから保育士試験を受けようと考えている方や、現在試験に向けて勉強している方のなかには、実際にどれくらい難しいのか、気になっている方も多いことでしょう。
そこで本記事では、これまで実施された保育士試験の結果をもとに、筆記試験・実技試験それぞれの合格率を詳しくご紹介いたします。
併せて、試験の問題数や出題範囲、合格に向けた勉強方法などもまとめましたので、ぜひ、参考にしてみてください。
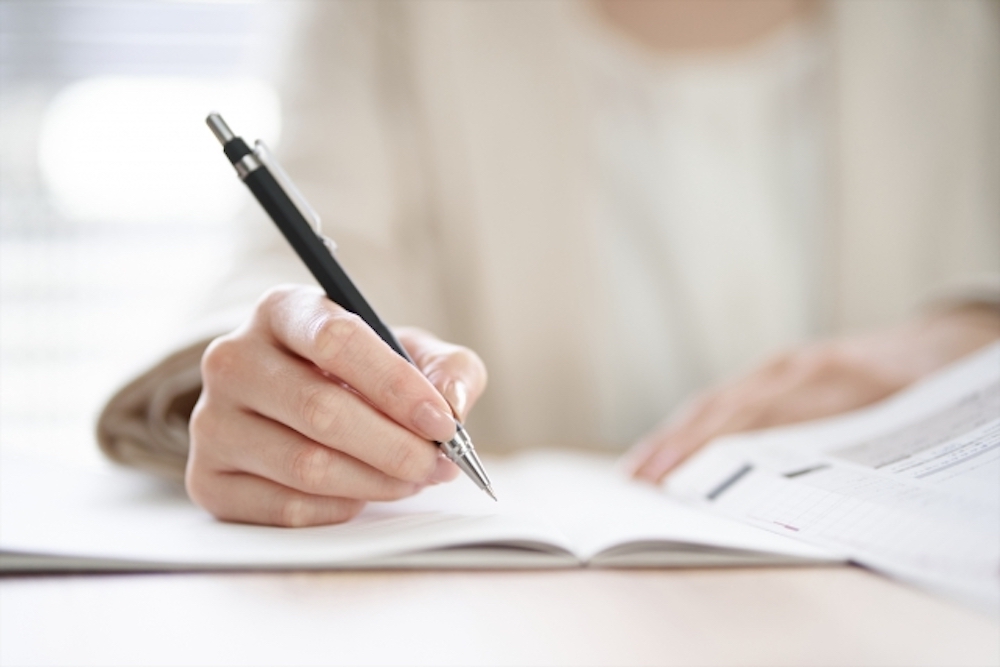
保育士試験の合格率をみる前に、まずは、保育士試験の概要を改めて押さえておきましょう。
保育士試験とは、児童福祉法に基づく国家資格「保育士資格」を取得するための試験のことです。試験日程は、春(前期)と秋(後期)の年2回で1回の受験料は12,950円。筆記試験と実技試験が実施され、両方に合格することで保育士資格を取得できます。なお、2022年度の試験日程は次の通り予定されています。
【前期試験】※2022年1月25日消印をもって受付終了
【後期試験】※受付期間:2022年7月5日~7月26日まで(当日消印有効)
筆記試験はマークシートによる択一式です。出題科目は全9科目、各科目100点満点中60点(6割)以上で合格となります。ただし、教育原理および社会的養護は50点満点で設定されているため、30点以上で合格です。
筆記試験の科目と出題範囲、および出題数の詳細は下記表を参照してください。
|
試験科目 |
出題範囲 |
出題数 |
|
保育原理 |
l 保育の意義及び目的 l 保育に関する法令及び制度 l 保育所保育指針における保育の基本 l 保育の思想と歴史的変遷 l 保育の現状と課題 |
20問 |
|
教育原理 |
l 教育の意義、目的及び子ども家庭福祉等との関連性 l 教育の思想と歴史的変遷 l 教育の制度 l 教育の実践 l 生涯学習社会における教育の現状と課題 |
10問 |
|
社会的養護 |
l 現代社会における社会的養護の意義と歴史的変遷 l 社会的養護の基本 l 社会的養護の制度と実施体系 l 社会的養護の対象・形態・専門職 l 社会的養護の現状と課題 |
10問 |
|
子ども家庭福祉 |
l 現代社会における子ども家庭福祉の意義と歴史的変遷 l 子どもの人権擁護 l 子ども家庭福祉の制度と実施体系 l 子ども家庭福祉の現状と課題 l 子ども家庭福祉の動向と展望 |
20問 |
|
社会福祉 |
l 現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷 l 社会福祉の制度と実施体系 l 社会福祉における相談援助 l 社会福祉における利用者の保護に関わる仕組み l 社会福祉の動向と課題 |
20問 |
|
保育の心理学 |
l 発達を捉える視点 l 子どもの発達過程 l 子どもの学びと保育 |
20問 |
|
子どもの保健 |
l 子どもの心身の健康と保健の意義 l 子どもの身体的発育・発達と保健 l 子どもの心身の健康状態とその把握 l 子どもの疾病の予防及び適切な対応 |
20問 |
|
子どもの食と栄養 |
l 子どもの健康と食生活の意義 l 栄養に関する基本的知識 l 子どもの発育・発達と食生活 l 食育の基本と内容 l 家庭や児童福祉施設における食事と栄養 l 特別な配慮を要する子どもの食と栄養 |
20問 |
|
保育実習理論 |
l 保育実習理論 l 保育実習実技 |
20問 |
なお、合格した科目には3年間の有効期限が設けられます。
実技試験は、筆記試験の全科目に合格した方のみ受験できます。音楽・造形・言語の3つから2科目を選択し、各科目6割以上(各50点満点中30点以上)の得点で合格となります。
実技試験の詳細は下記を参照してください。
|
出題科目 |
出題内容 |
求められる力 |
|
音楽に関する技術 |
幼児に歌って聴かせることを想定して、課題曲の両方を弾き歌いする |
保育士として必要な歌、伴奏の技術、リズムなど、総合的に豊かな表現ができること |
|
造形に関する技術 |
保育の一場面を絵画で表現する |
保育の状況をイメージした造形表現(情景・人物の描写や色使いなど)ができること |
|
言語に関する技術 |
3歳児クラスの子どもに「3分間のお話」をすることを想定し、4つのお話のうち1つを選択し、子どもが集中して聴けるようなお話を行う |
保育士として必要な基本的な声の出し方、表現上の技術、幼児に対する話し方ができること |
【参考】一般社団法人全国保育士養成協議会「令和4年実技試験概要」
各出題科目のテーマは事前に発表され、2科目選択したうえで出願します。当日に科目変更はできないため、自分のスキルを活かせる科目、自信をもって挑める科目をしっかり吟味して選びましょう。

保育士試験の概要を押さえたところで、ここからは、保育士試験の合格率を確認していきましょう。厚生労働省の発表をもとに、過去5年分の保育士試験受験者数・合格者数・合格率を下記表にまとめました。
|
試験年度 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|
2017年 |
62,555人 |
13,511人 |
21.6% |
|
2018年 |
68,388人 |
13,500人 |
19.7% |
|
2019年 |
77,076人 |
18,330人 |
23.9% |
|
2020年 |
42,272人 |
10,489人 |
24.8% |
|
2021年 |
83,175人 |
16,600人 |
20.0% |
※2020年度分は新型コロナウイルス感染症対応で前期筆記試験は中止されたため、後期試験のみの結果です。
【参考】
差はあるものの、保育士試験全体の合格率は概ね20%前後です。下記の通り、社会福祉士や介護福祉士など、同じ医療・福祉分野の国家試験と比べても、保育士試験の合格率は低めであることがわかります。
【ほかの国家試験の合格率との比較】
【参照】
では、筆記試験・実技試験それぞれの合格率もみていきましょう。
ここ数年、厚生労働省では筆記試験・実技試験それぞれの合格率を発表していません。ただし、公開されている2015年までのデータをみると、以下の通り筆記試験の合格率は20%前後を推移しています。
|
試験年度 |
筆記試験の合格率 |
|
2011年 |
16.2% |
|
2012年 |
21.0% |
|
2013年 |
19.3% |
|
2014年 |
21.3% |
|
2015年 |
25.2% |
そのため、筆記試験の合格率は概ね20%前後が目安と言えるでしょう。
【参照】
筆記試験同様、厚生労働省の公表しているデータをもとに、実技試験の合格率を下記にまとめました。
|
試験年度 |
実技試験の合格率 |
|
2011年 |
84.7% |
|
2012年 |
86.1% |
|
2013年 |
89.3% |
|
2014年 |
88.7% |
|
2015年 |
89.1% |
実技試験の合格率は例年9割弱を占めることから、保育士試験全体の合格率を下げているのは筆記試験であることが推測できます。では、どうして保育士試験、とくに筆記試験の合格率は2割程度と低いのか、次章でその理由を考察していきましょう。

前述の通り、保育士試験の筆記試験は、9科目と広範囲から出題され、さらにすべての科目で6割以上の点数を獲得しなければ合格できません。苦手科目を得意科目でカバーすることもできないため、幅広く、かつまんべんなく知識を身に着けておくことが求められます。
つまり、出題範囲の広さと全科目での高得点、この2つが保育士試験の合格率を低くしている大きな理由といえるでしょう。
【保育士試験の合格率が低いおもな要因】
また、保育士試験は、保育関連の大学や専門学校などを卒業していない方の受験が大半です。資格取得のためにはじめて保育や福祉の勉強をスタートする方も少なくありません。筆記試験の難易度を上げている背景には、こういったことも要因の1つと考えられます。
ちなみに、実技試験の合格率が約9割と高い理由には、全3分野から自分の得意なジャンルを2つに絞って受験できること、筆記試験合格後から実技試験日までの約1ヶ月間でじっくり対策できることなどが挙げられます。
なお、難易度が高い筆記試験ですが、一度合格した科目には合格した年を含めて3年間の有効期限が設けられています。
(例)令和4年に「保育原理」・「教育原理」の2科目に合格した場合
⇒令和5年・6年の試験では「保育原理」「教育原理」は免除
そのため、なかには最初から2~3年計画で保育士試験の合格を目指す方もいます。
現在、保育士試験は年に2回実施されており、3年間で最大6回の受験が可能です。保育士試験の合格率の高さ、試験範囲の広さに不安や悩みを抱えている方は、少しずつ時間をかけて合格科目を増やしていくのもよいでしょう。

最後に、保育士試験に合格するためにはどのような勉強方法をすればいいのかみていきましょう。ここでは、通信講座・通学講座・独学の3つをご紹介いたします。それぞれのメリットとデメリットを踏まえて、ぜひ自分にぴったりの勉強法をみつけてください。
民間企業が運営するスクールにて、通学制の講座を利用する方法です。講師との対面授業や講義のDVD視聴など授業体系はさまざまですが、保育士試験のノウハウが詰まった教材やカリキュラムで効率よく勉強していけるのが特徴。分からない問題はすぐに質問できるためより早く理解を深められること、同じ志の方が集まるためモチベーションを維持しやすいことなどもメリットです。
ただし、費用の高さが難点。スクールによっては20万円以上かかる場合もあります。また、社会人や主婦の方などにとっては、通う時間を確保することの難しさもデメリットと言えるでしょう。
なかには、実技試験対策のみの通学講座を設けているスクールもあるので、費用を抑えたい方はチェックしてみてください。
家庭でテキストやDVD、eラーニングを利用して勉強する通信講座もあります。保育士試験対策のノウハウが詰まった教材やカリキュラムで効率よく学習できるうえ、受講費は5~10万円程度と通学講座よりも費用を安く抑えられるのが特徴。また、分からない問題はメールなどで質問でき、定期的に添削課題があるので自分の弱点を把握しやすいのもメリットです。
決められた時間で勉強する必要がないので、社会人や主婦の方でも自分のペースで進めていけるでしょう。
ただし、通信講座は自分で進めていける分、途中で挫折してしまうデメリットも。サポート体制が充実していない通信講座だと独学とさほど変わらなくなってしまう場合もあるため、講座選びも重要です。
保育士試験対策用の参考書などはたくさん販売されているので、独学で勉強することも可能です。全国保育士養成協議会の公式ホームページには、保育士試験の過去問が公開されているため、試験問題の傾向も把握できるでしょう。
必要なものは、基本的に市販のテキストや問題集だけなので、通学講座や通信講座と比べて費用もかなり安く抑えられます。
ただし、独学の場合には、学習計画を自分で立てて進めていく必要があるため、モチベーションを保ち続けるのが難しい場合も。購入した参考書などが自分に合わないときには、買い替えも必要です。
また、保育に関する法改正など、試験に影響する情報を常に自分で収集していかなければならない点もデメリットの1つでしょう。
保育士試験の概要や合格率、合格に向けた勉強方法などを解説いたしました。保育士試験の合格率が例年20%前後と低めなのは、出題範囲が全9科目と幅広く、さらにすべての科目で6割以上の得点を獲得しなければならない筆記試験の難しさが要因の1つに考えられます。
しかし、2016年より保育士試験は年に2回実施されており、合格科目の3年間免除制度も設けられているので、合格に向けて挑戦できるチャンスも増えています。特に、はじめて保育を勉強する方にとっては、計画的に学習を進め、受験に臨むことが保育士試験合格のカギといえるでしょう。
なお、勉強法には、通学講座・通信講座・独学などさまざまなスタイルがあります。費用を抑えたい方は独学、できるだけ効率的に短時間で勉強したい方は通学講座など、ぜひ自分のライフスタイルに合う勉強法をみつけて、保育士試験合格を目指してみてください。
【参考】
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.