
保育士資格といえば、短大の保育科を卒業したり、通信講座などで取得する方法が一般的ですが、独学で保育士試験を受けても合格できるのでしょうか?
独学で勉強したい場合はどのような方法ですればよいのか、独学のメリットはあるのかを解説していきます。

保育士試験は難易度が高めな試験ですが、勉強法やモチベーションを維持する方法が分かれば、独学でも合格できます。
これからも需要が高まる保育士を目指し、独学で合格を目指しましょう。
まずは、難易度が高いとされる保育士試験について解説します。
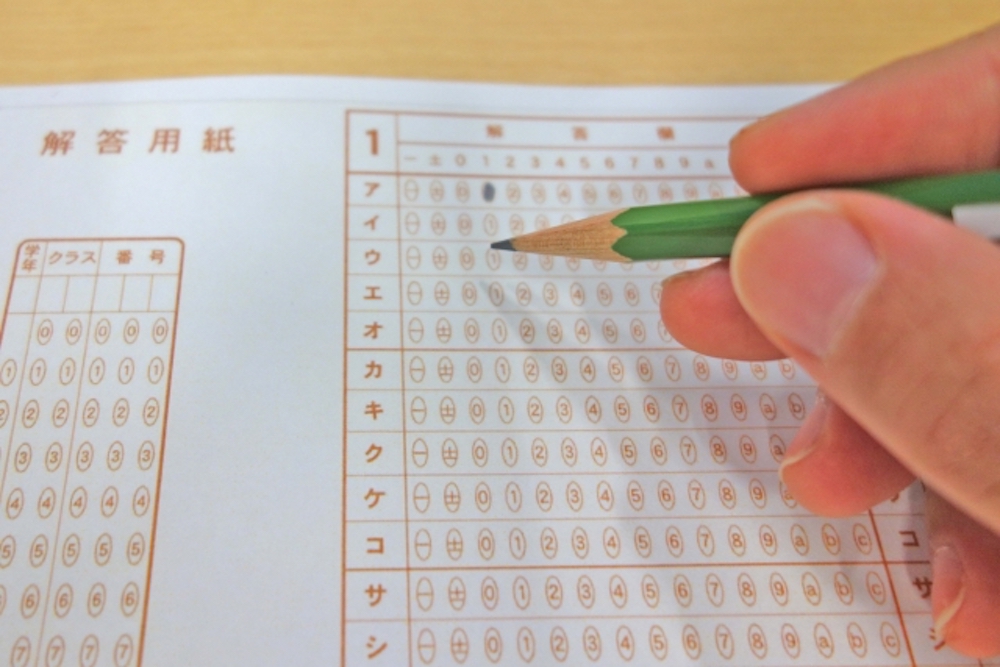
保育士試験には筆記試験と実技試験があります。
厚生労働省の資料によると、保育士試験の合格率はどの年を見ても筆記試験がおよそ20%、実技試験がおよそ80%で、両方合わせた合格率は20%前後です。
つまり、試験の難易度は高めだといえるでしょう。
なぜ難易度が高いのかというと、全科目で6割以上の点を取らなければ合格にならないからです。
筆記試験は全部で9科目です。それぞれ100点満点中60点以上が合格となります。
(「教育原理」「社会的養護」の2つは50点満点の構成で50点満点中30点以上が合格)
9科目全ての教科で6割以上の点を取らなければならないのが厳しいところでしょう。
【参考】
厚生労働省「保育士試験の概要」
厚生労働省「保育士試験実施状況(令和2年度)」
毎年同じ時期に保育士試験は開催されます。
|
日程 |
||
|
前期 |
筆記試験:4月中旬 |
実技試験:6月下旬 |
|
後期 |
筆記試験:10月下旬 |
実技試験:12月中旬 |
試験科目は以下の通りです。
筆記試験:
実技試験:(筆記試験合格者のみ受験。3分野のうち2分野を選択します)
【参考】厚生労働省「保育士試験の概要」
実技試験は、筆記試験が全て合格したら二次試験として受けることができます。
独学で始めたいけど、何から始めたらいいのか困ってしまいますよね。
まずは自分に合ったテキスト探しをすること、保育士試験までのスケジュールを立てることをおすすめします。
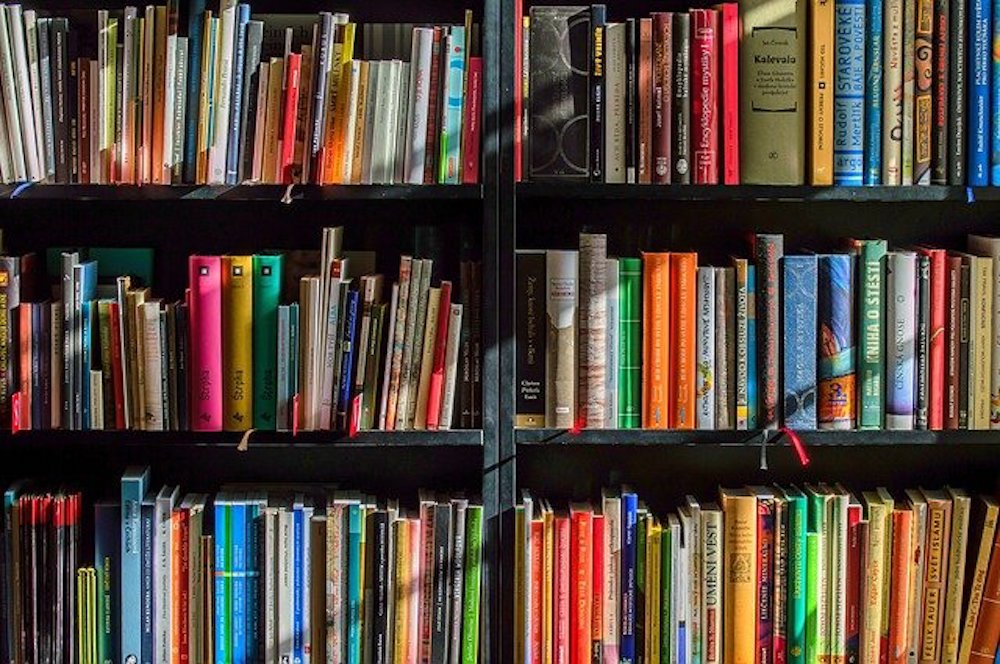
テキスト選びで大切なのは、最新のテキストを選ぶことと、自分に合ったテキストを選ぶことです。
まずは最新のテキストを選ぶべき理由ですが、分野によって問題や答えが変わりやすいからです。
特に、「保育原理」「教育原理及び社会的養護」「児童家庭福祉」「社会福祉」の問題は変わりやすいと言われています。
制度の改正によって解答が変わることがあります。
過去のテキストでも変わらない部分もありますが、最新のテキストの方が正確です。
ニュースや新聞などもチェックし、最新情報を集めるようにしておきましょう。
そして自分に合ったテキスト選びについてです。
解説が詳しいものや、イラストが豊富なもの、たくさんのテキストがあります。自分のすっと頭に入りやすい問題集を選ぶとモチベーションも維持できます。
これなら分かりやすいと思えるテキストを選ぶと勉強もしやすいでしょう。
また、過去問や予想問題、一問一答式の問題集もよいと思います。
インプットだけではなく、アウトプットも重要です。
中でも詳しい解説が載っているものがおすすめです。
正解した問題でも、どうしてその答えになるのかを確認できるからです。
テキストはインターネットでも購入できますが、書店で手に取りいくつか見比べながら購入した方がよいでしょう。

保育士試験は前期の筆記試験が4月中旬です。
4月の筆記試験に向けてスケジュールを立てていきましょう。
スケジュールを立てることによって、焦りや不安を抱えることなく、勉強配分を決めることができ、モチベーションの維持にもつながります。
独学で保育士試験の合格を目指すなら、1日1時間勉強すれば3ヵ月で達成できるといわれています。
あまりダラダラと長く勉強してもモチベーションは続きません。
短期集中の方が勉強効率は良いでしょう。
しかし社会人の方や、子育て中の方は勉強のためのまとまった時間を確保するのが難しいかもしれません。
焦らなくてもいいように、自分が一日のうちどのくらい勉強時間がとれるか考えておきましょう。
4月の試験に間に合わせるためにいつから勉強を始めたらよいのかを把握しておくと、自分のペースで勉強できます。
また、「1週間でここまで覚える」など小さな目標も立てておくとモチベーションも維持できるでしょう。
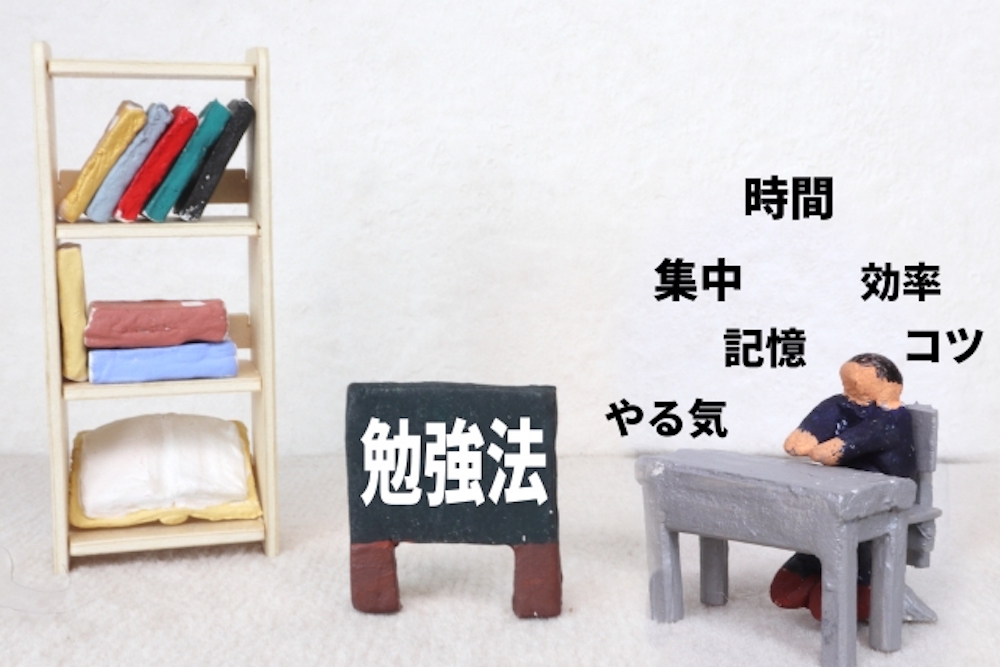
テキストを選び、スケジュールを立てたら早速勉強に取りかかることができます。
どのように始めたらよいか、おすすめの勉強法を4つご紹介していきます。
1つ目は見出しをざっくりと読んで、どのような内容かをおおまかに把握することです。
保育士試験は科目や範囲がとても広く、最初からじっくりやってしまうと時間が足りなくなってしまいます。
まず見出しを読んで、興味や得意不得意などを感じ取ってから勉強を始めましょう。
好きな科目から始めてみるとモチベーションが下がらずにやっていけるかもしれません。
またスケジュールを立てる際、不得意なもの苦手そうなものに時間を費やすよう組み立てていくこともできるでしょう。
2つ目はテキストを読んでインプットすることです。
見出しから内容をおおまかに把握できたら、広く浅くインプットしていきます。何度も繰り返し読むことによって、記憶に定着させていきましょう。
分からない内容があっても、とりあえず飛ばして読み進めることです。
全体を覚えるように読み込んでいきます。
3つ目はインプットの際に音読したり、耳で聞いたりすることがポイントです。耳で覚えると、より記憶が強化されると言われています。
音読したり、自分の声を録音したり、音声付きのテキストを使うのもよいでしょう。
目で見る、声を出す、耳で聞くなど、身体を使うインプットは脳を刺激するので記憶を定着させやすいです。
4つ目は一番重要なアウトプットです。
広く浅く覚えた内容を、すぐに過去問や予想問題でアウトプットします。
間違えた問題や分からなかった問題を、今度は深く解説を読み込んで理解していきます。
正解した問題でも、どうしてその答えになるのかが分からない場合は解説を深く読み込んで、深く理解することが大事です。
インプットよりもアウトプットに時間をかけた勉強ができるようにしていきましょう。
「広く浅くインプット、すぐにアウトプット、つまずきを深くインプット、再びアウトプット」の流れで問題をたくさん解くようにすると正解率が上がっていくでしょう。

独学にもメリットとデメリットがあります。
どのようなメリットやデメリットがあるのかみていきましょう。
独学のメリットがあったら勉強にもやる気が出てきますよね。
まずは独学のメリットをご紹介します。
独学は通学せずに勉強できます。社会人の方や子育て中の方などは、短大や養成所等に通うのが困難でしょう。
しかし独学なら、自宅で勉強ができるメリットがあります。
学校に通うためには時間が必要なので、コツコツと自宅で取り組める方にはぴったりな勉強法です。
独学は自分のペースで勉強できます。
社会人の方や子育て中の方は早朝や深夜、通勤途中、家事の合間などの隙間時間で勉強する習慣をつけると無理がありません。
通学のようにまとまった時間を作ることが難しい方におすすめです。
独学は費用を抑えることができます。
例えば短大では2年間で約250万円、通信講座の場合はテキスト代など6~7万円かかります。
独学ならテキスト代のみの数千円~1万円ほどで勉強が始められるため、費用は抑えられます。
独学でのメリットがあればデメリットもあるようです。
デメリットも知っておいた方がよいでしょう。
独学の最大のデメリットはモチベーションの維持が難しいところでしょう。
学校なら同じ目標を持つ友人がいて励まし合い、一緒に勉強できます。
通信講座の場合は、添削サービスやアドバイスなどがあります。
しかし、独学はモチベーションを維持するのは自分次第なので、挫折することもあるでしょう。
独学は最新情報を入手しづらいデメリットがあります。
保育士試験は時事問題が出されます。時事問題は最新情報が重要で、自分で予測するのは難しいでしょう。
通信講座や予備校などでは、試験の予測情報が入ってくるでしょうが、独学には限界があります。
勉強を進めていくと、どうしても分からない問題が出てくることもあるでしょう。そんなときでも教えてくれる人がいないという点がデメリットです。
通信講座なら講師の方に質問できますが、独学の場合は一人で解決しなくてはなりません。
独学は実技試験対策が困難です。一人で練習しても評価をしてくれる人がいません。
実技対策向けの動画などを参考に、自分なりに練習した様子を録画して見直すとよいでしょう。
本番は試験官の前で実技試験を行います。
緊張してしまう人は家族や友人の前で練習を積んだ方がよいでしょう。
保育士試験は合格率が20%前後と難易度は高めだといえます。
しかし、独学でも合格できるチャンスは十分にあります。
テキストやインターネットを活用して、自分にぴったりの勉強法をみつけましょう。
無理のないスケジュールをもとに、インプットとアウトプットを繰り返し、モチベーションを下げない努力が合格を目指すためのカギとなります。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.