
「子育てがひと段落したし、そろそろ保育士として復帰したい」
「一度は辞めたもののやっぱり保育士として子どもたちと関りたい」など、
保育士への復帰を希望している方が多く見受けられます。
しかし、以前と同じように働いていけるのか、さまざまなことに不安を感じて二の足を踏んでいる方もいることでしょう。
そこで今回は、保育士の復帰の現状や保育士として復帰するメリット、復帰する際のポイントなど、保育士の復帰事情について詳しく解説いたします。
保育士として安心して復帰するための方法をじっくりと探っていきましょう。

保育士として復帰を考えた際に気になるのが、保育現場を離れている保育士、ブランクのある保育士の需要が実際にあるのかですよね。
そこでまずは、保育士の復帰の現状から詳しく確認していきましょう。
厚生労働省の発表によれば、保育士資格を有しながら現在保育士として勤務していない潜在保育士の数は全国に95万人ほどいるとされています。
そして日本の大きな社会問題となっている待機児童や保育士不足を打開するためには、新たな保育士の育成に加えて潜在保育士の職場復帰が必要です。
このため政府や地方自治体では、潜在保育士の再就職を支援する政策を数多く実施しています。
潜在保育士の再就職支援に関するおもな取り組み例は次の通りです。
【参考】厚生労働省「保育を支える保育士の確保に向けた総合的取組」
つまり、現在の保育現場では潜在保育士の需要が極めて高く、一人でも多くの職場復帰が期待されています。
野村総合研究所が平成30年に全国の保育士7,210人を対象に行ったアンケート調査によると、現在就労していない潜在保育士のうち、約6割もの方が「今後保育士として働いてみたい」と回答していることが報告されています。
復帰を希望する理由として上位を占めた回答は次の通りです。
潜在保育士の多くが「いつかは子どもに接し、子どもの成長に関われる保育の現場に復帰したい」と職場復帰を望んでいることがわかります。
【参考】野村総合研究所「潜在保育士の6割が保育士としての就労を希望」P.8

では国をあげて潜在保育士の復帰が望まれ、さらに多くの潜在保育士が働く意欲をもっているのにも関わらず、実際に復帰する人は少なく、潜在保育士の増加傾向が続いているのはなぜでしょうか。
ここからは、潜在保育士の復帰を妨げているおもな不安要素について確認していきましょう。
厚生労働省の資料では、過去に保育士として働いていた方の退職理由が次の通り報告されています。
仕事量の多さ(27.7%)や労働時間の長さ(24.9%)などが上位を占めていることから分かる通り、保育士は拘束時間が長く、とてもハードな仕事です。
そのため、とくに結婚や出産などで一度保育士を辞めている方にとっては、家庭と仕事を両立していけるかが大きな不安要素となってしまうのでしょう。
なお同資料では、過去に保育士として働いたことのある方が回答した再就職する際の希望条件についても次の通りまとめられています。
勤務日数・勤務時間・雇用形態(パート・非常勤採用)など、いずれも働き方を重視した回答が並んでいますよね。
希望の働き方ができる職場をいかに見つけるかが潜在保育士復帰のひとつのキーポイントになっているようです。
最近では最新の技術や知識を積極的に取り入れている保育園も増えています。
そのため退職後かなりブランクが長い保育士は、自分の知識や経験が現在の保育現場で活用できるか、足手まといにならないかと不安を感じることがあるようです。
保育士が子どもたちを安全に保育していくためには、職場のスタッフのほか、保護者の方とも良好な人間関係を構築することが求められます。
とくにブランクが長いと、自分より年下の職員や保護者の方と接したりする場合もあり、うまくなじんでいけるか不安を抱えてしまう方も多いようです。
子どもたちを抱っこしたりおんぶしたり、日中は一緒に園庭で踊ったり走り回ったりと、保育士の仕事は体力勝負です。
そのため、自分の健康や体力に不安を感じ、復職を諦めてしまう方も多いようです。

保育士として復帰するにはさまざまな不安要素が伴いますが、復帰によって得られるメリットがあることも忘れてはいけません。
ここからは、保育士が復帰するメリットを探っていきましょう。
一般的に仕事の世界では新卒の方が採用されやすいイメージがありますが、保育現場では一度現場を離れた保育士の復職でもたくさんチャンスがあります。
経験のある保育士は即戦力として期待されるからです。
たとえブランクが長い方でも、働いていくなかで自然に体が思い出し、保育士として積み上げてきた経験をぞんぶんに発揮できるでしょう。
保育士を至急補充しようと努めている保育園などでは、新卒よりも経験のある潜在保育士の方が優遇されるケースもありますよ。
また、若手の保育士より年齢を重ねた保育士の方が保護者の方に安心感を与えられるのもメリットのひとつです。
すでにご説明した通り、待機児童や保育士不足問題を早急に解決すべく、国や自治体が主導となって潜在保育士に向けたさまざまな復帰支援策が実施されています。
たとえば、次のような補助制度をとっている自治体もありますよ。
⇒保育士として再就職する際に必要な費用の一部を無利子で貸付。2年間の継続した就労で返済が全額免除。
⇒潜在保育士として復帰する際に未就学児を保育園などに入所させた場合、保育料の一部を無利子で貸付。2年間の継続した就労で返済が全額免除。
上記のほか、未就学の子どもを優先的に保育施設へ預けられる制度なども実施されています。
さまざまな支援策をうまく活用すれば、精神的にも金銭的にも安心して復帰することができるでしょう。
保育士の確保と離職率の低下を図るため、平成25年より保育士の処遇改善制度が進められています。
保育士の給与は全業種の平均値と比べると今なお低い傾向にあるものの、平成22年時点で325万円だった保育士の平均年収は、令和元年には364万円と大幅に上昇していることが報告されています。
また同時に、ICTシステム(インターネットを活用した業務支援システム)の導入支援なども進められており、保育士の業務負担が軽減している保育園も増えてきています。
これらのことから、保育の現場はさまざまな視点から改善されてきており、賃金面、業務内容ともに好条件で働ける可能性があるのもメリットのひとつといえます。
待機児童や保育士不足は全国的に深刻な問題となっています。
子どもを保育園に預けられないために働けず、途方に暮れている家庭も少なくありません。
そのため、保育士として復帰することがそのまま社会貢献につながるのもメリットのひとつといえます。社会に求められる存在として、自信と誇りを持って働いていけるのではないでしょうか。
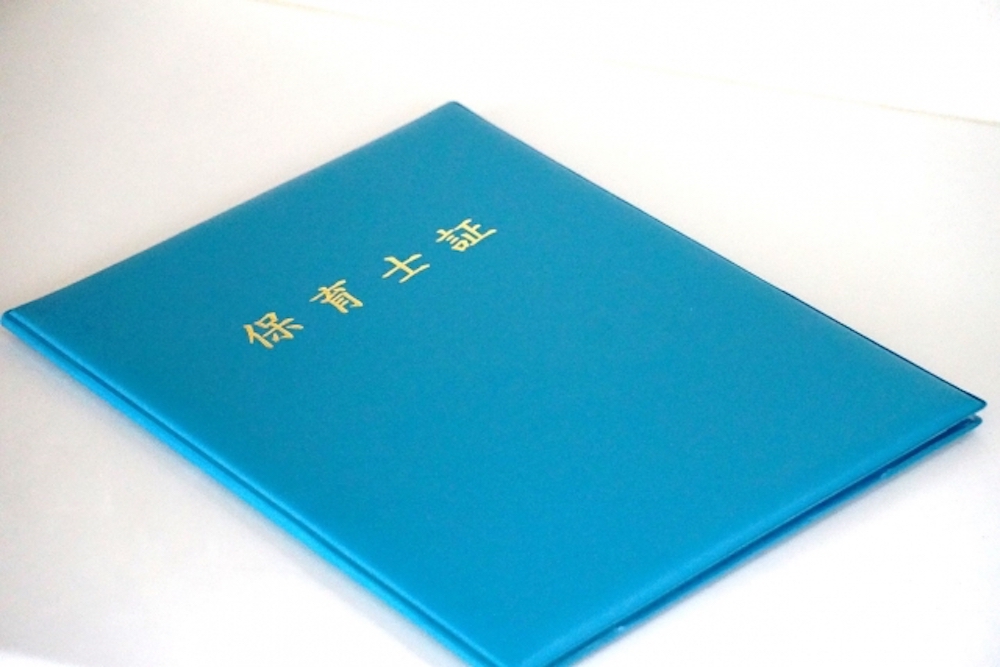
ここからは保育士として復帰する際のポイントを解説いたします。
保育士として自信をもって復帰するために、ぜひ参考にしてみてくださいね。
復帰後に「こんなはずではなかった…」と後悔することのないよう、保育士として復帰する際の希望条件を明確にしておきましょう。
たとえば、次のような項目が挙げられます。
長くいきいきと働いていくために、自分のライフスタイルと照らし合わせながらじっくりと考慮してみてください。
ブランクがあると、保育士として以前習得した知識や経験が活かせるのか、不安に感じるものです。
現場では過去とやり方が変わっている場合もあるので、新しい技術も柔軟に取り入れていく姿勢が大切です。
そのため、復帰前には自治体や民間事業などで開催されている再就職セミナーや実技研修などを受講しておくとよいでしょう。
保育士の知識を最新のものへとアップデートし技術を改めて身につけておけば、自信をもって復帰に望めます。
また研修やセミナー会場では、自分と同じような境遇の方が集まるため、復職への不安を相談したり情報を交換したりできる方と出会える可能性もありますよ。
ブランクがあり、久しぶりに保育現場へ復帰する場合には、生活リズムを整えておくことも大切です。
保育士は体力勝負の仕事なので、心身ともに健康でなければ働き続けることが難しくなってしまう場合もあります。
早寝・早起き、十分な睡眠に3食しっかり食べる、という基本的な生活習慣を整えておくことはもちろん、休みの日にストレッチやウォーキングなどをして体力をつけておくとよいでしょう。
児童福祉法の改正により、平成15年11月29日より保育士の定義が変わっています。
改正以前は、保育士試験合格者や養成施設卒業者に交付される「保育士資格証明書」を持っていれば保育士として働くことができました。
しかし改正後の現在、保育士として働くためには、都道府県知事に登録申請手続きを行い、「保育士証」の交付を受けることが必須です。
そのため、復帰を検討している方は必ず「保育士証」が手元にあるかを確認しておきましょう。
登録申請手続きを行っていない場合、保育士証が見当たらない場合には、都道府県知事委託の保育士登録機関「登録事務処理」センターへの問い合わせが必要です。
なお、申請書の受付から保育士証の発行までおよそ2ヶ月程度かかってしまいます。書類に不備があるとそれ以上の日数がかかってしまうので要注意。
できるだけ早めに手続きを済ませておくと安心です。
【参考】都道府県知事委託 保育士登録機関 登録事務処理センター「保育士の定義」
保育士として復帰したくても、なかなか踏み出せずにいる方も多いことでしょう。
小さい子どもがいる方は、これまでの生活スタイルが変わることで育児と仕事を両立できるのか悩みを抱えてしまうのも無理はありません。
復帰を考えているのなら、まずは何が不安なのか、不安を解消するためにはどうすればよいのかをひとつひとつじっくりと考えてみることから始めましょう。
保育士への処遇は年々改善され、以前よりも多くの施設で給与がアップしていますし、社会から求められる保育士として働くことはそのまま社会貢献に、そしてやりがいにもつながっていくことでしょう。
希望条件を明確にし、復帰に向けて自信をもって進んでみてください。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.