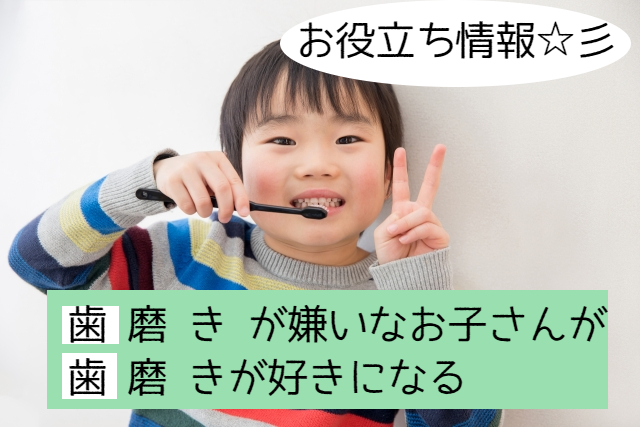
子どもたちへの歯磨き指導も保育士の仕事の1つです。
この記事では歯磨き指導を保育園で実施するねらいやポイントを解説していきます。
また、実際に歯磨き指導が始まってもすぐに飽きてしまう子どもたちも多いため、歯磨きを楽しい時間にするためにおすすめの指導方法もご紹介いたします。

保育園では、子どもの乳歯が生えそろった頃に歯磨き指導を実施しています。
歯磨き指導は子どもにとってどんなメリットがあるのでしょうか?
1つ目のメリットは「乳歯を健康な状態に保てること」です。
「乳歯はいつか永久歯に生え変わるものだから、そこまで重視しなくても…」と考える人もいるかもしれません。
しかし、乳歯は子どもの発育に大きく影響します。
乳歯は食べ物をかむこと以外にも、さまざまな機能を担っています。
例えば、味覚の発達や言葉を正しく発音するためにも乳歯は大切な役割があるのです。
つまり、子どもの健やかなや発育のためには、健康な乳歯が必要なのです。
2つ目のメリットは「永久歯への波及効果」があるという点です。
乳歯の虫歯と永久歯の虫歯には関連があるとされており、乳幼児期の歯磨き指導による習慣づくりは非常に重要だと考えられています。
また、虫歯があることにより食べ物をしっかりとかめなかったり、発音に影響が出るケースも少なくありません。
永久歯へのトラブルを防ぐためにも、保育園では歯磨き指導を実践しています。
【参考】歯の健康|厚生労働省

保育園では歯磨きに関する指導やイベントへの取り組みを実施しています。
厚生労働省・文部科学省・日本歯科医師会・日本学校歯科医会が実施している「歯と口の健康週間(通称:虫歯予防デー)」や、歯科医師を招いての「歯磨きイベント」などが例として挙げられます。
保育園が子どもに歯磨き指導をする理由は主に2つです。
それぞれの理由から、歯磨きの必要性をチェックしていきましょう。
保育園で歯磨きを取り入れていると言っても、いきなり歯ブラシを使った歯磨きをするわけではありません。
まだ歯磨きの習慣がついていない段階では、ガーゼなどで口の中のミルクのかすを拭きとります。]
次の段階では、食後にうがいを促します。
こうして段階を踏むことで、子どもが口の中をきれいにする習慣が少しずつ身についてくるのです。
習慣が身につくと、「食後に口の中をきれいにしないと落ち着かない」という気持ちが湧いてきます。
歯磨きが子どもの生活習慣の一部になるよう、段階を踏んで歯磨きを促していきましょう。
歯は食事や正しい発音などに欠かせない大切なものです。
しかし、言葉だけで伝えても、子どもにはその大切さがいまいち分からないでしょう。
そんなときは、絵本や教材を使って説明する方法がおすすめです。
絵本や音楽を使えば、歯磨きのコツはもちろん、虫歯の怖さや歯磨きの心地よさなども子どもに伝わりやすくなります。
子どもの歯磨きへのモチベーションも高まるので、積極的に取り入れていきましょう。

保育園で歯磨きを指導し始める年齢は、何歳なのでしょうか?
ここでは、多くの保育園が歯磨きを指導する子どもの年齢や、年齢ごとの歯磨き指導のコツを解説します。
保育園の歯磨き指導は3歳児からスタートします。
乳歯が生えそろう時期は、2歳6カ月頃~3歳です。
子どもの乳歯が生えそろった時期に指導を始めるのが多いようです。
保育士が歯ブラシを支えながら、子どもと一緒に歯ブラシを動かします。
4歳になると子どもが1人で歯磨きができるので、保育士は仕上げのみ行うことがほとんどです。
5歳になると慣れてきて歯磨きをサボってしまう子どもいるので、きちんと取り組めているかチェックしましょう。
保育園では0~2歳児には本格的な歯磨き指導は行いません。
0~1歳児の場合、離乳食やおやつの後は歯磨きの代わりにお茶を飲みます。
歯磨き指導を積極的に実施している保育園では、保育士が歯茎マッサージをして、ガーゼや専用の歯ブラシで歯を磨いてあげることもあるようです。
保育園によっては、2歳から歯磨き指導をスタートするところもありますが、2歳頃は自我の芽生えによって自己主張が強くなる「イヤイヤ期」です。
この時期に歯磨きを無理強いすると、歯磨きがきらいになってしまう可能性も高くなってしまいます。
2歳児から歯磨きをスタートさせる場合は、口の中をすすぐ習慣や、歯ブラシに慣れることを最低限の目標にして、子どものペースに合わせながら指導しましょう。

言葉での解説や歯磨きの援助だけでは、歯磨きの大切さや歯磨きの方法を子どもに分かりやすく伝えることはできません。
次の5つのポイントを踏まえて歯磨き指導を実践していきましょう。
上記のポイントから、子どもが楽しみながら歯磨きに取り組めるコツをチェックしていきましょう。
歯磨き指導をする際は、まず「歯磨きに興味を持ってもらうこと」が大切です。子どもの興味を引くために、歯磨きをテーマにした紙芝居や絵本を読み聞かせましょう。
紙芝居や絵本には、言葉だけでなくイラストも描かれているので、歯の役割、歯の大切さなどを子どもに分かりやすく伝えられます。
保育士が言葉で伝えにくい部分も、紙芝居や絵本を使えばわかりやすく説明できるので、大変おすすめです。
歯磨きの時間の前に読み聞かせをして、子どもに「歯磨きって楽しそう!」「歯磨きやってみたい!」という意欲を引き出しましょう。
紙芝居や絵本のほか、エプロンシアターやパネルシアターを使って歯磨きをレクチャーするのもおすすめです。
エプロンシアターやパネルシアターは、子どもに大人気のアイテムなので、興味を引くにはぴったりです。
歌や人形の動きに合わせて、歯ブラシを動かす動作や、歯を磨く順番なども教えられます。
歯磨きをテーマにしたエプロンシアターやパネルシアターのキットがたくさん販売されています。
もちろん、1から自分で手作りしてもOKですが、製作の手間を考えるとキットを購入した方がよいでしょう。
オークションサイトやハンドメイド専門の通販では、すでに完成したエプロンシアターやパネルシアターが販売されているので、「製作する時間がない」という人はこちらで購入してみるのをおすすめします。
歌を通して、歯磨きの大切さや楽しさを伝えてもよいでしょう。
歯磨きをテーマにした子ども向けの歌を歌いながら、子どもたちにその場で歯を磨く動作をしてもらったり、歯ブラシの持ち方を練習すれば、自然と歯磨きの仕方が身につきます。
紙芝居や絵本では、歯磨きの流れを伝えられますが、音楽を使えば実践的な歯磨きの練習を促せます。
とはいえ、歯磨きの習慣がない子どもに、いきなり音楽に合わせて練習させるのは、なかなか難しいでしょう。
まずは紙芝居や絵本、エプロンシアターやパネルシアターで歯磨きへの興味を引いて、次に音楽に合わせて練習…と段階を踏んで指導するのが効果的です。
簡単な歯磨きクイズを取り入れると、子どものやる気をさらに引き出せます。「虫歯になると、どんなことが起きるかな?」「歯磨きは、食べる前と食べた後のどっちにやるんだっけ?」など、歯磨きの基本的な情報を元に、子どもでも分かるような内容を取り上げていきましょう。
もちろん、歯磨きに対して何の知識もない状態でクイズを出すのはNGです。
絵本やエプロンシアターなどで基本的な知識を教えてから、クイズを出しましょう。
歯磨き中に音楽をかけると、子どもが楽しい気分で歯を磨けます。
歯磨きをテーマにした音楽や、子どもに人気の歌をCDで流しましょう。
「音楽が流れている間は歯磨きをする」「音楽が止まったら、歯磨きの時間はおわり」とルールを定めておくのもおすすめです。
可能であれば、保護者の方に子どもの気分が上がるような歯ブラシを用意してもらいましょう。
子どもの中には、どうしても歯磨きが苦手な子どももいます。
子どもがなかなか歯磨きをしないときは、その子どもが好きなキャラクターの歯ブラシを用意してもらうのがおすすめです。
お気に入りの歯ブラシがあれば、保育士も「ほら、○○(キャラクター)の歯ブラシで歯を磨こうよ!○○も待ってるよ?」と声をかけて歯磨きを促せます。
歯磨きは「乳歯を健康な状態に保つ」「丈夫な永久歯が育つ」ために大切な健康習慣です。
保育園で行う歯磨き指導のねらいは、子どもに歯磨きをする習慣を身につけるだけでなく、歯の大切さを伝えることです。
歯磨き指導の際は、絵本やエプロンシアター、音楽などを使って、子どもが楽しんで歯磨きできるように工夫していきましょう。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.