
業務量が多く、日々忙しく働く保育士。「有給休暇を取得して、リフレッシュしたい…」と思っても、なかなか取得する余裕がなかったり、体調不良以外では取得しにくい職場の雰囲気があったりと、思うように有給休暇が取得できないという悩みを抱えている方は多いようです。
そこで今回は、保育士の有給休暇事情を徹底解説いたします。有給休暇の基本から保育士の有給休暇取得率の現状、さらに、有給休暇を申請する際のポイントまで詳しくご紹介いたします。

有給休暇とは、一体どのような休みのことなのでしょうか。「給与の出る休暇」、「欠勤にならない休暇」などなんとなくは分かっていても、しくみまでしっかりと理解している方は意外に少ないようです。
そこでまずは、有給休暇の基礎知識を深めていきましょう。法律上の定義が分かれば、有給休暇がより取得しやすくなるはずです。
厚生労働省によると、有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」と呼び、一定条件を満たしした労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことを指します。
労働者が有給休暇を申請することで取得でき、「有給」という名の通り、取得しても賃金が減額されない旨が『労働基準法(第39条)』によって明確に定義されているのが特徴です。
有給休暇が付与される条件は次の通りです。
上記2点を満たしていれば、業種や職種、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態にかかわらずすべての労働者が有給休暇付与の対象となります。
有給休暇の付与日数は、労働者の勤続年数や雇用形態によって変わります。前項でご説明した「雇入れの日から6ヵ月間継続して勤務していること・6ヵ月間の全労働日のうち、8割以上出勤していること」の2つの条件を満たした労働者には、まず10日間の有給休暇が付与され、1年経過するごとに下記表に該当する日数が付与されます。
|
雇入れから起算した継続勤続年数 |
有給休暇付与日数 |
|
6ヵ月 |
10日間 |
|
1年6ヵ月 |
11日間 |
|
2年6ヵ月 |
12日間 |
|
3年6ヵ月 |
14日間 |
|
4年6ヵ月 |
16日間 |
|
5年6ヵ月 |
18日間 |
|
6年6ヵ月以上 |
20日間 |
なお、条件を満たす労働者には雇用形態にかかわらず有給休暇が付与されるものの、パートやアルバイトなどで所定労働日数が少ない場合(週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満)には、下記表の通り比例的に付与されます。
|
|
週所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
雇入れから起算した継続勤続年数(年) |
||||||
|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
|||
|
有給休暇付与日数(日) |
4日 |
169~216日 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
|
3日 |
121~168日 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
2日 |
73~120日 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
|
1日 |
48~72日 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
有給休暇は、毎年決まった日数が付与されますが、有効期限は「2年間」と定められているため要注意。当年中に取得しなかった有給休暇は翌年に繰り越されるものの、2年間を超えてしまうと消滅してしまいます。
働き方改革の一環で労働基準法が改正され、2019年4月より、雇用主は、年10日以上の有給休暇を付与される労働者に対して、うち5日間は確実に取得させることが義務化されました。
同法律によって、有給休暇を取得する時期については、労働者の意見を尊重するよう努める旨も定められています。
この規定により、今後、有給休暇が取得しやすい環境へと変化していくことが期待されます。これまで有給休暇の取得にためらいを感じていた保育士の方も、より気軽に取得できるようになっていくのではないでしょうか。
有給休暇の基礎知識を深めたところで、ここからは保育士の有給休暇取得率の現状をご説明いたします。一般的に、保育士は有給休暇が取得しにくいというイメージがありますが、実際のところはどうなのでしょうか?早速、みていきましょう。
2017年9月に公布された『全国保育協議会 会員の実態調報告書 2016』によると、保育士(正規職員)における有給休暇の平均取得日数は次の通りです。
|
平均日数 |
2日以内 |
3~6日 |
7~9日 |
10~15日 |
16~20日 |
21日以上 |
無回答 |
|
全体 |
2.9% |
31.3% |
28.8% |
25.3% |
6.8% |
1.4% |
3.5% |
|
公設公営 |
3.2% |
40.7% |
31.5% |
17.9% |
3.1% |
0.7% |
2.9% |
|
公設民営 |
3.1% |
30.8% |
22.5% |
31.3% |
7.5% |
1.8% |
3.1% |
|
民設民営 |
2.6% |
23.9% |
27.2% |
30.7% |
9.6% |
1.9% |
4.0% |
保育施設全体をみると、平均取得日数は31.3%の「3~6日」が最も多く、平均取得日数が6日を下回る施設も3割超存在していることがわかります。ちなみに、同じ年に厚生労働省より報告された『平成28年就労条件総合調査の概況』をみると、労働者一人あたりの平均取得日数は8.8日です。この結果を比べると、やはり保育士の有給取得率はやや低めといえるでしょう。
ただし、上記表を施設別にみてみると、公設民間および民設民営の保育園で最も多い平均取得日数は「10~15日」(全体で25.3%)という結果もでており、保育士全体の有給取得率が極端に低いというわけではないようです。
つづいては、現場で働く保育士の声に目を向けてみましょう。2018年度の『東京都保育士実態調査報告書』によると、現在の職場に対する改善希望事項として36.5%もの方が「未消化休暇(有給等)の改善」と回答していることが報告されています。詳細は下記表を参照してください。
【保育士における現在の職場の改善希望事項(トップ5を抜粋)】
|
|
給与・賞与等の改善 |
職員数の増員 |
事務・雑務の軽減 |
未消化(有給等)休暇の改善 |
勤務シフトの改善 |
|
全体 |
65.7% |
50.1% |
49.0% |
36.5% |
32.0% |
|
公設公営 |
61.9% |
53.9% |
55.0% |
49.8% |
29.2% |
|
公設民営 |
64.9% |
48.2% |
48.5% |
36.0% |
4.2% |
|
民設民営(社会福祉法人) |
65.8% |
48.5% |
36.0% |
34.2% |
33.9% |
|
民設民営(株式会社) |
71.2% |
53.2% |
44.4% |
26.7% |
32.1% |
|
民設民営(NPO法人) |
61.8% |
43.9% |
35.1% |
26.0% |
29.4% |
|
民設民営(その他) |
59.6% |
43.6% |
40.1% |
27.7% |
27.5% |
未消化(有給等)休暇の改善を希望は、全改善希望事項のなかでも4番目に多い回答であり、やはり有給休暇の取得について不満や不安を抱えている方は少なからずいるようです。ただし、施設別にみると、公設公営では49.8%と約5割を占めるものの、民設民営(NPO法人)では26.8%と保育園によってバラツキも。
保育園のなかには、無理のないシフトを組む・職員の配置人数を増やす、などといった対策をして有給休暇を充実させている施設がある一方、園全体に取得しにくい雰囲気がある・人員不足で取得している暇がないなど依然として取得しにくい施設もあり、有給休暇の取得しやすさについては勤務先の保育園による差が大きいことが分かります。

すでにご説明した通り、有給休暇とは、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。日々ハードな業務をこなしている保育士にとって、有給休暇をしっかりと取れずにいるのは大きな負担となってしまうことでしょう。
保育士の有給休暇の現状を把握したところで、ここからは、有給休暇が取得しにくい保育園で働くデメリットについて探っていきます。
子どもたちを日中に保育するほか、お便り帳への記入や週案・月案などの書類作成、壁紙作製に職員会議…と、日々膨大な業務に追われている保育士。保育園によっては土曜日に隔週で出勤し、週にたった1日しか休めない場合もあります。そのような状態で有給休暇も思うように取れないとなると、心身ともにリフレッシュしている時間がありません。
旅行したり趣味に没頭したりと、プライベートを充実させることは「明日からまた頑張ろう」という活力につながるものです。リフレッシュできないままがまんして働いていては、心身ともに疲弊し、仕事への意欲も効率も下がってしまうのではないでしょうか。
有給休暇を取得しにくいことは、保育士の早期退職をうながす原因となってしまう場合もあります。心身の疲弊が積み重なると、やがては退職や転職という形で表れてしまうのも無理はありません。
なお、離職者がでると、保育園では人材不足によって新たな募集をかけなければならなかったり、他の職員にさらなる負担がかかって別の離職者がでてしまったりするケースも。
有給休暇を取得しにくい保育園で働くことは、本人にとっても、保育園にとっても悪影響を及ぼす可能性があるのです。
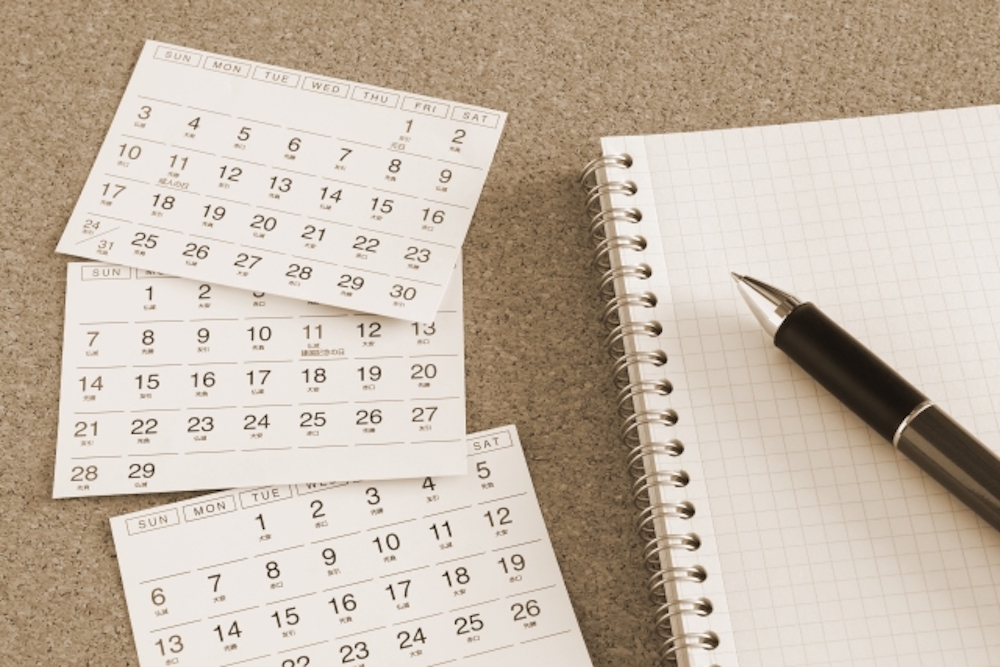
最後に、有給休暇を申請する際のポイントをご紹介いたします。今後の有給休暇を少しでも取得しやすくするため、ぜひ実践してみてください。
保育士が有給休暇を取得する際には、時期やタイミングを考慮することが大切です。たとえば、次のような時期に有給休暇を申請するのは避けた方が無難です。
業務量が多くなる時期にはそもそも休んでいる時間がありませんし、申請しても許可されない可能性があります。また、風邪やインフルエンザが流行する冬の季節には、体調を崩して休んでいる保育士の分を他の保育士でカバーする必要があるため、やはりリフレッシュ目的の有給休暇を申請するのは避けた方が無難でしょう。
イベントが比較的少ない時期、お盆などの世間的な長期休暇で預かる子どもの人数が少なくなる時期など、休みを取っても負担とならないタイミングをぜひ見極めてみてください。
職場の人間関係を良好にしておくことも、有給休暇を取得しやすくするための大切なポイントです。
普段から積極的にコミュニケーションを図り、お互い気軽に、そして気持ちよく有給休暇取得の相談ができるような環境づくりを心がけてみてください。
有給休暇を取得する場合には、休む日程をできるだけ早めに同僚や先輩へ伝えておくようにしましょう。ギリギリのタイミングで伝えると、仕事上のトラブルを引き起こす場合もあり、相手に不快や不信感を与えてしまう場合があります。
有給休暇の日程が決まった時点で連絡し、最低限の引継ぎなどを、余裕をもってすませておくとよいでしょう。
有給休暇とは、心身を休めて、しっかりとリフレッシュするために用意されている休みのことです。がまんしたまま働き続けていては、仕事の効率も意欲も低下して悪循環に陥ってしまうことでしょう。
「有給休暇を消化したいけど、なんとなく申請できない…」と悩んでいる方は、申請する時期やタイミングを今一度考慮してみてはいかがでしょうか。普段からコミュニケーションを図り、同僚や先輩と気軽に有給休暇の相談ができる関係を築いておくのもよいでしょう。
また、なかには有給休暇消化率100%を目指している保育園などもあるので、転職を検討してみるのも良策です。
有給休暇で心と体をしっかりと充電し、明日の活力へとつなげていきましょう。
【参考】
全国保育協議会「全国保育協議会 会員の実態調査 報告2016」
厚生労働省「労働基準行政全般に関するQ&A > 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」
厚生労働省「【リーフレットシリーズ労基法39条】年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 分かりやすい解説」
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.