
2015年4月にスタートした「子ども・子育て新制度」により、新たに創設された「放課後児童支援員」。学童保育施設での遊びと生活を支援し、健全育成を行うための専門資格のことで、現在、学童保育施設には1名以上の「放課後児童支援員」を配置することが義務付けられています。
そこで今回は、「放課後児童支援員」をまるごと徹底解説。放課後児童支援員になるには?仕事内容は?など、放課後児童支援員について詳しくご紹介いたします。

まずは、「放課後児童支援員」の基礎知識を深めていきましょう。
冒頭でもお伝えした通り、「放課後児童支援員」とは、学童保育施設で働く際の専門資格です。2015年4月、「子ども・子育て新制度」のスタートに伴い、新たに創設されました。これまで、学童保育施設への有資格者の配置についてとくに規定はありませんでしたが、現在では、『放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準』に基づき、各施設に1名以上の放課後指導支援員の配置が義務付けられています。
学童保育施設の施設数・登録児童数が、ともに増加の一途をたどっている今日、放課後児童支援員は注目度の高い資格のひとつと言えます。
学童指導員とは、学童保育施設で働く職員のことです。以前は、とくに必要とされる資格がなかったため、学童保育施設に携わるすべての方が「学童指導員」と呼ばれていました。
しかし、2015年4月に放課後児童支援員の資格が創設されるとともに、学童保育施設への一定数以上の放課後指導支援員の配置が義務付けられたため、有資格者を「放課後児童支援員」、無資格者を「学童指導員」と呼び分けるようになっています。
なお、学童指導員と放課後指導支援員の大きな違いは資格の有無で、仕事内容にあまり差はありません。

放課後指導支援員の基本を押えたところで、ここからは早速、資格の取得方法を確認していきましょう。なお、放課後児童支援員になるには、『放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準』で定められている条件を満たし、かつ各自治体が行う研修を修了することが求められます。
まずは、資格取得条件についてみていきましょう。放課後児童支援員になるには、下記いずれかの条件に該当している必要があります。
【資格の取得条件】
これらの資格条件を簡単にまとめると以下のようになります。
【参考】
厚生労働省「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」
放課後児童支援員の資格取得条件を満たした方は、各自治体が実施する研修を受講する必要があります。なお、この研修の目的は、放課後児童支援員として業務を遂行するうえで、必要最低限の知識・技能を習得し、それらを実践する際の基本的な考え方や心得を認識すること。
では、日程やカリキュラム、科目など、研修の詳細を確認していきましょう。
研修の日程は、各自治体によって異なります。詳細は、お住いの自治体のホームページ等を参照してください。
カリキュラムは、下記の6分野・16科目・24時間(1科目90分)で構成されています。
【研修の項目・科目】
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解
子どもを理解するための基礎知識
放課後児童クラブにおける子どもの育成支援
放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力
放課後児童クラブにおける安全・安心への対応
放課後児童支援員として求められる役割・機能
各自治体で異なりますが、1回の研修日数は4~8日程度。原則として2~3ヵ月以内で実施されます。
また、保育士・社会福祉士・教員免許などすでに取得している資格に応じて、研修科目の一部を免除することも可能です。
【参考】厚生労働省「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修ガイドラインの概要」
研修受講料は原則無料です。ただし、テキストを購入する場合、また会場までの交通費、昼食費などは自己負担となりますので注意しましょう。
【参考】
東京都福祉保健局「令和2年度東京都放課後児童支援員認定資格研修について」
LEC東京リーガルマインド「2020年度 神奈川県放課後児童支援員認定資格研修」

最後に、放課後児童支援員の仕事内容や勤務時間、雇用形態などを詳しく確認しておきましょう。
放課後児童支援員の仕事は、就労等で保護者の方が家にいない子どもたちへ、下校後や長期休暇中に安心して過ごせる場所を提供することです。厚生労働省によると、放課後児童支援員に必要とされる役割は次の通り。
これらをもとに、具体的な仕事内容を把握していきましょう。
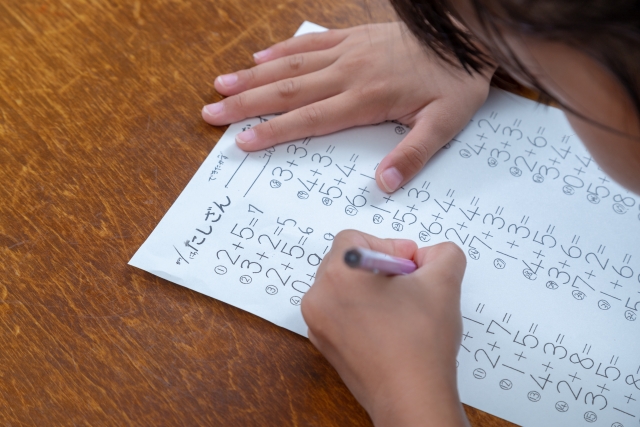
宿題などの勉強や遊びを見守りつつ、基本的な生活習慣を身につけさせて健やかな心と体の成長をサポートします。
また、家庭との連携を図ることも放課後児童支援員の重要な仕事のひとつです。仕事をしている保護者の方にとって、子どもの普段の様子を把握したり小さな変化を感じ取ったりするのはなかなか難しいもの。
学童保育施設での様子を伝え情報交換することで、安心して預けられる環境を作り、保護者の方とともに子どもの成長をサポートします。
学童保育施設によって放課後児童支援の仕事内容に違いはありますが、一般的には次のような1日を過ごします。
【1日のスケジュール例】
|
14:00頃~ |
小学生入室 |
学校が終わった子どもを出迎え、宿題等にとりかからせます。 |
|
15:30頃~ |
おやつ |
宿題終了後におやつを提供します。 |
|
16:00頃~ |
自由時間/イベント等 |
室内で工作したり、外でドッジボールなど、子どもそれぞれの自由時間をサポートします。 |
|
17:00頃~ |
帰りの会/帰宅開始 |
帰りの会を行い、保護者が迎えに来た子どもを見送ります。 |
学童保育の閉所時間は18~19時頃。保護者のお迎えが来た子どもから見送ります。
放課後児童支援員の勤務時間は、平日は小学校の授業が終わるお昼頃から学童保育施設の閉所時間(18~19時頃)まで。土曜日や夏休みなどの長期休暇は朝から閉所時間までが一般的です。
学童保育施設で働く職員は、非正規雇用の割合が高く、給与の低さや人材不足も問題視されています。内閣府が2016年に実施した調査によると、放課後児童支援員1人あたりの給与額(年額/手当・一時金込)は次の通りです。
ただし、2017年には「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」が創設され、経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組みも設けられており、今後の処遇改善も期待できます。
【参考】
厚生労働省「放課後児童支援員の役割及び職務と補助員との関係」
内閣府「平成28年度 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に係る実態調査の集計結果概要について」
厚生労働省「「放課後児童健全育成事業」の実施について/別紙9」
子どもたちにとって学童保育施設は、学校が終わった後、家庭代わりに安心して帰れる場所です。そして、放課後児童支援員は、子どもたちの心と体の成長をサポートする、重要でやりがいのある仕事のひとつ。
子どもたちの成長に携わりたい!と考えている方は、資格取得条件を確認のうえ、ぜひ研修を受講してみてはいかがでしょうか。
なお、実施場所・実施時期・申し込み方法等は各自治体によって異なります。気になる方は、お住まいの自治体のホームページをチェックしてみてくださいね。
【参考】
厚生労働省「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」
内閣府「すくすくジャパン!子ども・子育て支援新制度について」
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.