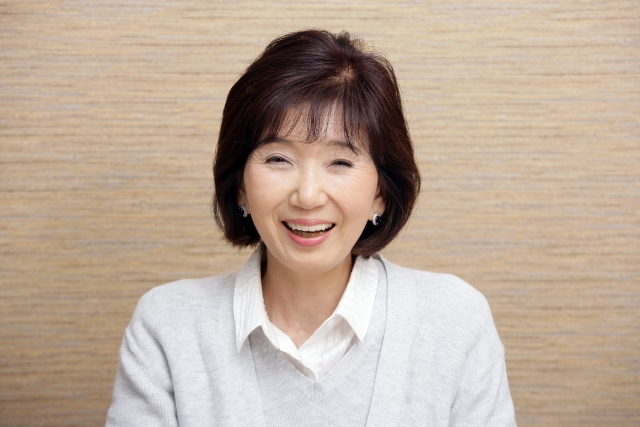
保育園で働く保育士の中にはでゆくゆくは園長を目指している方もいるでしょう。この記事では保育園を取りまとめる園長の役割や仕事内容、そして園長になるための条件などを解説します。また給料事情やメリット・デメリットなども合わせてご紹介いたします。

現役保育士の中には「園長ってどんな仕事をしているのか、いまいちよく分からない…」という人は案外多いのではないでしょうか?確かに、現場の保育士は日頃の保育業務で忙しく、園長と関わる機会も少ないため、園長がどんな仕事を担っているのか、疑問に思うこともあるでしょう。
ここでは、保育園の園長の主な役割や具体的な仕事内容についてピックアップしていきます。
簡単に言うと、園長は「保育園の運営・経営をする責任者」です。
など
園長はこれらのような幅広い業務を担っています。常に書類作成や、保育士から提出された書類のチェックなどに追われおり、さらに園長会議にも出席するため、非常に多忙です。そのため、園長になるためには「複数のタスクを同時に行う力」「スケジュール管理能力」「効率化を考えた働き方」が必要です。
さらに、保育園のトップとして現場の保育士たちを導くリーダーシップや、よりよい現場を作り上げるための「選択力」「問題解決能力」も必須と言えるでしょう。
保育園経営にまつわるお金の管理は、園長の仕事の中で特に重要な業務です。具体的には、国・自治体からの補助金や事業収入(保育料・実費徴収)を始めとする「収入」から、スタッフの給与の「人件費」、教育研究経費・管理経費などの「経費」を差し引いて「予算計画」を立てます。
中には、事務員が予算計画を立てて園長が承認をする保育園もあるようです。マネジメントに興味のある人やスキルを実践したい人にはぴったりの役職と言えるでしょう。
現場の保育士の指導も園長の役割です。定期的に面談を行ったり、評価シートや目標管理シートを使って保育士の意欲を高め、研修の参加を促すなど、指導方法はさまざまです。
また、園長は人事業務も行います。転職サイトに求人を掲載したり、転職エージェントや派遣会社のスタッフと面接の日程を話し合ったり、面接当日に求職者と面接をしたり、採用に関する一連の業務を担います。実習生やボランティアの受け入れや対応をすることもあるでしょう。さらに、法人・会社内の人事異動も携わるケースもあるため、常に「人」と関わる役職なのです。
入園希望者の見学や、入園相談の対応も園長の業務です。保育園の責任者として、見学の電話対応を行い、当日に園内を案内します。また入園説明会では園長として、保育園の方針や理念を保護者の方へ説明する場面もあります。保育園の「顔」として人前に出るのが園長の大きな仕事です。
外部との連携や交流も重要な業務です。例えば、系列園のイベント参加、同じ法人・会社内の会議、地域の人との交流などです。
また、市役所などの行政機関へ、保育園運営に必要な補助金の相談をすることもあります。虐待問題には児童相談所、障がい児保育の際は専門療育機関と連携をとります。ケースによってさまざまな機関との「つながり」が必要です。
保育園でトラブルや事故が起きた際は、園長が責任者として保護者対応をすることもあります。ときにはクレーム対応を求められるケースもあるでしょう。園長は保育園の総責任者なので、その対応によって保護者の方の反応は大きく変わります。問題を解決するためには、保護者の方の気持ちに寄り添い、誠意をもって対応する姿勢が求められます。
こうした「対話力」を身に付けるためには、日頃の保護者の方との密接なコミュニケーションが大切です。

「いつか園長になって保育園を経営したい!」という保育士のために、園長になるための条件と給与について取り上げます。
園長になるための条件は保育園によって異なりますが、一般的には保育歴10年以上の経験が必要だと言われています。私立保育園の場合、保育士資格以外に必要な資格は特にありませんし、保育現場は常に人手不足です。園長候補はそこまでハードルが高い目標ではありません。保育園の求人には、園長候補の応募条件に「保育士経験3~5年以上」と記載されていることがあります(多くは私立保育園)。
公立保育園の園長になるまでのルートを大まかに解説します。
公立保育士は「地方公務員」です。まずは、公務員試験に合格して、正社員の保育士として実務経験を積むことが必要です。もちろん、保育士資格も必須です。
ちなみに、保育所設置認可等事務取扱要綱によると、公立保育園の園長の条件は以下のように定められています。
公立保育所(公設民営を含む。)の施設長となる者は、児童福祉事業に2年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
ただ、実務経験2年で園長になれる人はほとんどいないため、10年ほど経験を積んで出世する、というのが一般的なルートです。
【参考】保育所設置認可等事務取扱要綱
公立保育園で園長になるためには、保育士として経験を積んだ後、昇格試験を受ける必要があります。しかし、公立保育園自体が少ないため、「狭き門」になっているのは事実です。
続いて、私立保育園の園長になるまでのルートを解説します。
保育所設置認可等事務取扱要綱によると、私立保育園の園長の条件は以下のように定められています。
つまり、「保育士としてフルタイム勤務で働いた経験のある人なら目指せる」ということです。保育士資格は必須ではありませんが、園長として信頼を得るためには、保育士資格や幼稚園教諭一種免許状などを取得した方が有利でしょう。
【参考】保育所設置認可等事務取扱要綱
主任やフロアリーダーなど、リーダー職の経験を積んでから、園長に昇進する保育士が多いようです。実務経験がある場合は、「園長候補」の求人に応募したり、自身で保育園を新設するという方法もあります。
幼稚園・保育所等の経営実態調査では、公立・私立保育園の園長の平均月収は54万円となっています。年収は650万前後です。ただ、無認可保育園の場合は国や自治体からの補助金が受け取れないので、月収は400万円前後です。ただ、保育士の年収とは大きな差があるため、やりがいも感じるでしょう。
【参考】厚生労働省「幼稚園・保育所等の経営実態調査結果(収支状況等)」
ここでは、園長になるメリット・デメリットをピックアップしていきます。園長職を目指す前に理解しておきましょう。

園長は責任の大きい役職ですが、よい部分もたくさんあります。ここでは、園長のやりがいやメリットを3つ取り上げていきます。
園長になれば、自分の理想とする保育園を作ることができます。園長は保育園内の最高責任者であるため、保育園の特色や理念、経営方針を自由に設定できます。「食育・音楽・運動に力を入れたい」「異年齢保育がしたい」「こんなイベントがしたい」など、自分の目標や理想がある人には、ぴったりの役職でしょう。
園長は保育園のリーダーとして、保育士の育成に携わることができます。接する対象が子どもから保育士に変わるため、始めは戸惑いを覚えるかもしれません。しかし、今後の保育業界を支えていく若手の保育士たちが育っていく姿を見れば、達成感を感じるでしょう。
保育士はほかの業種と比べると給料が低いため、やりがいが感じられず保育士を辞めてしまう人もいます。しかし、園長になれば収入が増えるため、やりがいが実感できるでしょう。

園長はやりがいのある役職ですが、その分大変なこともあります。ここでは、園長の悩み3つを解説します。
園長は園内の最高責任者であるため、保育方針や経営方針に大きな影響力があります。しかし、その責任はすべて自分が背負うことになります。ちょっとした選択ミスで、保育園の経営が不安定になったり、保育士たちの負担を大きくしてしまう可能性もあります。
園長になった際は「自分の選択は周囲に影響を与える」ことを忘れてはいけません。
「保育士の育成」は苦労がつきものです。現場がミスをしたり、トラブルを対処できない場合は、園長が代わりに対応する場面も出てきます。また、保育士同士の人間関係が悪い場合、園長が介入して解決しなければなりません。このような「新人教育」「チーム育成」が延長にとって大きな負担となってしまうのは仕方ありません。
園長になると、系列園や近隣の保育園のイベントに出席したり、卒園児が小学校へ入園した際に入学式で祝辞を披露したり、とにかく外部との関りが増え忙しくなります。さらに、会議や研修の機会が増えるので、書類の作成やチェックが終わらないこともあるでしょう。
園長を目指すなら、複数のタスクを同時にこなせる力や、スケジュール管理能力を身に付けておきましょう。
園長は責任が大きい役職ですが、保育園の運営や保育士の育成など、やりがいのある業務に携わることができます。保育士向けの転職サイトでも、園長候補の求人はたくさんあります。
現在勤めている職場で園長を目指すなら、今のうちにスキルと経験を積んでおきましょう。新しい保育園で園長を目指すなら、園長候補を募集している求人に応募してみてはいかがでしょうか?
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.